江戸川建設業協会
更新日:2025/6/2
【江戸川区の現状と課題】
今年1月1日に能登半島地震が発生した。震度7の揺れに対し、被害を受けた住宅数は8万棟を超えたことが明らかになった。この現状を受け、江戸川建設業協会の内海憲市会長(内海建設)は、「同じ規模の地震が、江戸川区を震源地に起きたらどうなる?」と危惧している。東日本大震災以降、江戸川区でも緊急対策が整備されてきた。しかし、「これが機能しているか否か?」を熟慮すると、内海会長は「肌感覚では機能できていないのが現実」と考える。理由は、災害発生直後に行政と協会が連携できる部署が現時点では存在していないこと。「本来なら区長直轄の組織として、危機管理部がこれを担えれば協会との懸け橋になり、スムーズな連携が取れるはずだ」と打開案を提示する。現行のルールでは、震度5以上の地震が起きると会員企業は体育館に出向き、避難所の開設が可能かどうかの調査を始められること。また、道路上に亀裂・破損があるかなどの点検にしか関与できないという現実に直面する。内海会長は、「調査段階で終わり、自分たちの権限も付与されていないため、その後の対応が後手に回り、指示を待つだけの状況に陥ってしまうのは明白。現時点では、協会と行政とでは意見を擦り合わせする場すら無いので、日常的に綿密な連携を取れる状況を確保することで、緊急時の対応が実現できるようにしたい」と具体策を提案する。
【危機管理に対する日本と台湾の相違】
台湾で4月3日に起こった花蓮地震の際、現地の行政は日頃から官民双方の連携が取れている関係性を活かし、発生から3時間後に避難所を開設できた。避難所には、40以上の個室テントが設置され、テント内には複数のベッドを配備。温度調節できるシャワー用のテントや、日用品や食料も充実させるなど、パーソナルスペースの確保を重点的に考えた施策により、被災者のストレスを極限まで減少させる配慮ができていたという。
花蓮市の職員は、共通の「防災LINEグループ」に入っており、ここには民間団体も参画。タイムリーに画像が上がることで、現場の状況をリアルタイムで把握でき、誰がどのように対応をすべきか、即座に関係部門に指示が下りたようだ。内海社長は、「日本では、自治体職員の負担が大き過ぎることが、避難所の体制整理に時間を要する原因の1つと考えている。日本の場合は、避難所開設から運営まで、民間ではなく自治体の職員が担っており、テントや簡易ベッドなども物資として手配しなければならない。一連の作業は、場合によっては道路の状況を見ながら、トラックや燃料の確保なども考える必要に迫られる。行政・自治体に権限が集中しているが故に、最前線に向かうべき建設企業が指示待ちの状態が続くという悪循環に陥っている」と日本と台湾を比較する。台湾の行政は、1999年の台湾大地震後、日本の制度を参考に防災計画を立て自主防災組織を構築した。今回の迅速な活動を「行政の力は小さい。民間と協力を進めてきた日頃の成果を出せた」と台湾行政もコメントを出しており、台湾の危機管理に対するスタンスから日本が参考にすべき点は多い。
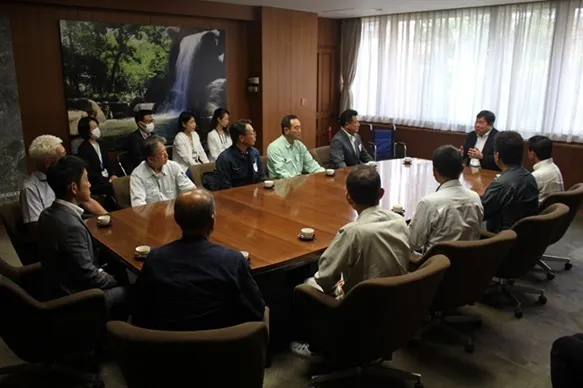
【区全域200ヶ所に防災用カメラを設置】
江戸川区は今年度から2年計画で、大規模地震が発生した際にリアルタイムで区全域の情報収集するため、自営通信網による防災用カメラを200ヶ所に設置している。カメラは半径300メートル毎に、避難所となる学校や区施設の屋上などに置く予定であり、情報収集の迅速化や、被害が甚大な地域の理解を狙いとしている。これまで被災状況の把握に多大な時間・人員を割いてきた対応策となっており、災害時に途切れない自営通信網システム・自立運転可能なソーラー蓄電池も導入することで、災害現場や避難所との通信も実現する。内海会長は、「基本的には素晴らしい政策で応援する。しかし、重要な点は情報分析後に、どのような初動を見せられるかだ。江戸川区は、行政が災害ハザードマップを公表する必要がある程、緊急災害時に混乱が予想される地域。台風の発生や震度5以上の地震が起こらなくても、迅速に現場へ向かえる体制を作らなければ、国民の生命が失われることに繋がる」と見立てを述べる。これは荒川氾濫の危機と常に隣合わせの江戸川区だからこそ、いの一番に取り掛かるべき事案であり、状況次第では政令や条例などに関わる話になり得る。「平時にこそ正しい施策を」という内海会長の具体的な提案は含蓄があり、有力な選択肢として留意すべきである。

【東日本大震災の教訓】
災害発生後、江戸川建設業協会として最後に現場に駆り出された機会を「東日本大震災で、千葉県浦安市の住宅街が液状化で機能不全に陥った時」と内海会長は振り返る。当時の浦安市長から江戸川区長に直接要請が届いたこと。また、当時の西野会長の指揮によりスムーズな連携が取れたことで協会員が現地に駆け付け、長期間インフラの復旧支援に集中できた好事例となっている。しかし、敢えて内海会長は「緊急時での出動だった為、誰も口にすることはなかったが、現段階で通常の労務費+危険手当を付けるなど、出動するに当たり行政は事前のルールを明文化しておく必要がある」と具体的な提案をする。前もって行政は協会に「3時間以内に必ず連絡をするので、体制を整えてほしい」と通達しておけば、次の連絡時に協会側から「何人までなら出すことが可能」など、1往復のやりとりで全て完結することが出来る。3-11の際はこのような規則はなく、当時協会の会長を務めていた西野氏自身の判断で急場を凌げたが、他区・他県との相互協力が不可欠になる今後を考慮すると、今すぐにでも実施に踏み込むべき懸案事項である。

【国民の生命を救う事前準備を】
内海会長が様々な懸念点や課題を述べる理由の根幹には、「首都圏で能登半島地震クラスの規模の震災が起これば、事前準備によって救えたはずの命を失う形になるから」と断言する。現状では災害時、初動で現場に辿り着くのは自衛隊というケースが多く、地元を熟知し身軽に動けるはずの建設企業がこれを担えない現実が歯痒いという本音もあるようだ。「既に様々な企業と提携している行政も多いので、今後は災害発生直後でも明確な活動ができるよう文書化し、活動に制限を与えないよう配慮することが最悪な事態の回避に直結する」と語気を強める。一事が万事。たった1つの綻びが、取り返しの付かない現実に繋がった過去は枚挙に暇がない。「行政・区民とは常に連携できる距離を維持し、本音かつ活発な意見交換を行える関係を継続する。これが被害を最小限化にできる第一歩」という明確なスタンス。内海会長の言葉からは、「インフラを下支えするのは建設業。都民・区民の方々が安全・安心に暮らせる礎は、我々が担っている」という自信とプライドで溢れている。災害直後でも建設企業が命を守る迅速な活動に入れるよう、平時である現段階から万全の体制を準備するべきである。

江戸川建設業協会のホームページ: https://www.edokenkyoo.com/
ハザードパップ: https://www.city.edogawa.tokyo.jp/documents/519/henkoutenjp.pdf
業界リーダーに迫る: https://corp.craft-bank.com/cb-souken/edogawa
ニュース記事: https://corp.craft-bank.com/cb-souken/edogawa-3
この記事を書いた人
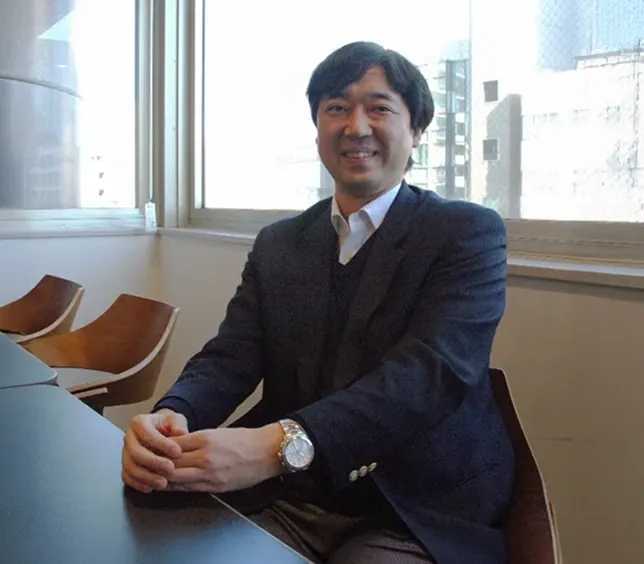
クラフトバンク総研 編集長 佐藤 和彦
大学在学時よりフリーライターとして活動し、経済誌や建設・不動産の専門新聞社などに勤務。ゼネコンや一級建築士事務所、商社、建設ベンチャー、スタートアップ、不動産テックなど、累計1700社以上の取材経験を持つ。
2022年よりクラフトバンクに参画し、クラフトバンク総研の編集長に就任。企画立案や取材執筆、編集などを担当。現在は全国の建設会社の取材記事を担当。








