下水道管路管理業協会
更新日:2025/6/2
▼目次

【大同団結を超えて】
2026年に日本下水道管理管路業協会の長谷川健司氏(管清工業㈱・代表取締役)が、会長に就任してから20年を迎える。旧建設省と議論する中、旧3団体(下水道管路施設維持管理協会・全国下水道管路維持技術協会・日本テレグラウド協会)が大同団結する形で、1987年に前身である下水道維持協会が発足した。当時、長谷川会長は一技術委員として団体を下支えしており、管路管理という業態が社会に認知・浸透される前夜に立ち会っていた。その後、協会は社団法人としての船出を迎え、長谷川会長は周囲からの推薦により会長に就任。祖父からの教えでもある「自分だけが儲かる仕組みを作るのでなく、パイ全体の拡大を意識すること」を忠実に守り、協会の会員数・自社(管清工業㈱)双方の売り上げを3倍近くに引き上げることに成功した。会員を含めた同業者には、これまで会得してきた利益を上げるノウハウを積極的に公開し、社員には「これまでの知見は全て吐き出した。私たちは、その更に先を目指そう!」と叱咤激励する長谷川会長。新規参入を希望する企業からは、「協会に入れば、実績が上がると聞いた」との声が上がり続けている。

【公益社団法人に移行】
日本下水道管理管路業協会は2009年、公益社団法人に移行した。下水道業界で先陣を切る形で着手した決断。社団法人の中では新参者の立ち位置でもあった為、存在感を際立させるには、周囲からの見え方や組織としての有り様、活動内容を大幅に変える必要があったという。長谷川会長は「これまで以上に団体として堂々と『談合は一切やらない』との姿勢を示す必要性があった。健全な競争ができる組織だと内外に示せたことで、更なる発展を目指せると確信した」と本音を述べる。公益社団法人は、目的そのものでなく通過点。これにより策定してきた『下水道管路管理マニュアル』や『下水道管路管理積算資料』などの発刊図書は、公的な側面を持つように変化し、協会活動の柱でもある『災害時復旧支援協定』も高く評価されるようになった。この結果、会員には専門工事業者だけでなく、ゼネコンやコンサルタント、プラントメーカーなども参画。現場での調査診断・補修・応急対応だけでなく、計画・設計・統括管理など、様々なプレイヤーと関われる場として協会が機能し、これまでにない領域のパッケージ化も実現した。
【災害復旧支援活動と下水道管路管理技士認定制度】
長谷川会長は、「協会の2大事業として、災害復旧支援活動と下水道管路管理技士認定制度を位置付けている」と語る。1993年1月に発生した釧路地震からは、会員が被災地に駆け付け清掃や点検・調査などの復旧支援活動を行うようになった。現在、地方公共団体などと締結した災害時復旧支援協定は900以上にのぼる。緊急事態の際、地場に根差した会員企業が即座に現場に向かえるよう、全国での協力関係を強化し続けてきた結果が、各地の行政からの信頼感に繋がっている。長谷川会長も「98年に下水道管路管理技士認定制度を開始してからは、常にバージョンアップを心掛け、資格を取得した企業が優先的に仕事を回す仕組み化もできた。今後も『管路管理に想定外は起き得ない』という事実を基にした提案を行いたい」と意向を述べる。協会では、災害発生時の責任者は被災経験者を担当にしており、国から連絡が入り次第、どのような状況に陥っても各地の会員に出動の指令が出せる体制を備えている。一朝一夕では組み立てられない信用と実績が、人命救助の上では不可欠だと理解できるエピソードである。

【緊急出動を定価ベースで予算化】
甚大な災害が発生し会員が現地支援に向かう決定が出ると、協会は国との協議も踏まえて、あらゆる項目の単価を定価ベースで請け負える契約を交わしている。これは今まで団体によっては、自社の仕事を投げ打ち救助活動に出向いたにも関わらず、手弁当だったことで作業者のモチベーションが急落するケースを知る長谷川会長が、国交省・財務省と綿密な折衝をしたことで始まった取り扱いである。行政との交渉は困難を極めることが予想された。しかし、長谷川会長は「過去のデータに基づいた上で工種ごとの綿密な積算資料を提出し、論理的な説明を実施したら、すぐに納得して頂けた」と述懐する。非常事態に会員が躊躇なく現場に行けるシステムを作らなければ、尊い命が失われる可能性が高まる。同体制を作り上げて以降は、天変地異が起きると国・行政側は協会に連絡を入れ、協会側はそれに準じて地場企業に出動依頼を掛けられるように変化。迅速な救助に邁進できる循環を構築した瞬間となった。過去の事例と真摯に向き合い、工期延長も含め役所との緊急事態における予算化を決めた背景には、綺麗事抜きに全てはビジネスによって動き得るという現実が理解できる。1次調査は地元自治体、2次調査は資格取得企業など、役割も細分化されており、昨年1月に発生した能登半島地震でも、この体系化された組織により現地を救うことができた。
【専門分野を超えた連携を】
昨今、協会内には設計事務所やコンサルタントなど、様々な業種が入会する形となった状況を勘案し、長谷川会長は「専門工事業者・ゼネコン・コンサルタントの全てが、更に各々を上手く使いこなせるよう、知識・技術の習得を深めた連帯を深めてほしい」と組織運営上の課題を提起する。具体的には、専門工事業者に対しては、最前線を熟知している長所を他業種にも還元すること。ゼネコンには、スマートシティ・官民連携のPPPを実施する上での最適な工事業者の動かし方。コンサルタントには、設計だけでない管路管理の計画策定などを挙げる。「業界の特色だと想像するが、やはり各種の縄張り意識はまだ強い。同じ協会内に所属するメンバーとして、より深い部分で協調ができれば可能性は倍増すると確信している」と断言する。共同企業体(JV)などを経ると、刺激を受けて見違える顔つきになる会員も多い。難局打破を体験することによる成長の実感。経験を通じた育成と団体の発展を重視する長谷川会長の目標は常に高く、今後の事業展開における鍵になりそうだ。

【持続的に発展できる地盤を強化する】
2013年に笹子トンネルの落下事故が発生以降、「建設から管理の時代」に流れが移り、老朽化対策に取り組まなければ、大惨事が巻き起こると国内に共有された。インフラが重要視された状況だからこそ、長谷川会長は「我々が正念場を迎える時」と気を引き締め、このチャンスを活かそうと意気込みを見せる。今まで点としてしか動けなかったが、近年では複数年契約が前提になるなど顕著な変化もある。2024年4月に、水道整備・管理行政が国土交通省・環境省に移管された現実も追い風に、「日々、軌道修正を繰り返していくため、問題点は1度でなく、何度も指摘し続ける姿勢を貫き解決策に導きたい」と強い意志を示す。
会長就任から20年を迎えようとしてもなお最前線で積極的な活動を見せる長谷川会長に、「後継者を考え始めているか?」と聞くと、「一切ない」と即答された。「『周囲から辞めてほしい』と言われれば、すぐにでも退く覚悟はある。しかし、私が後継者を指名すれば、任命者がプレッシャーになるリスクを避けたい」と配慮を見せる。会社の経営者でもあるが、口にする話題の6割以上が自社でなく業界全体に関することのようだ。下水道事業を支えるため、長期的なスパンで持続的に発展できる地盤を作り上げられるか。長谷川会長が担うべき仕事はまだ多く残されており、その一挙手一投足から目が離せない。
日本下水道管理管路業協会のホームページ:https://www.jascoma.com/
管清工業のホームページ:https://www.kansei-pipe.co.jp/
この記事を書いた人
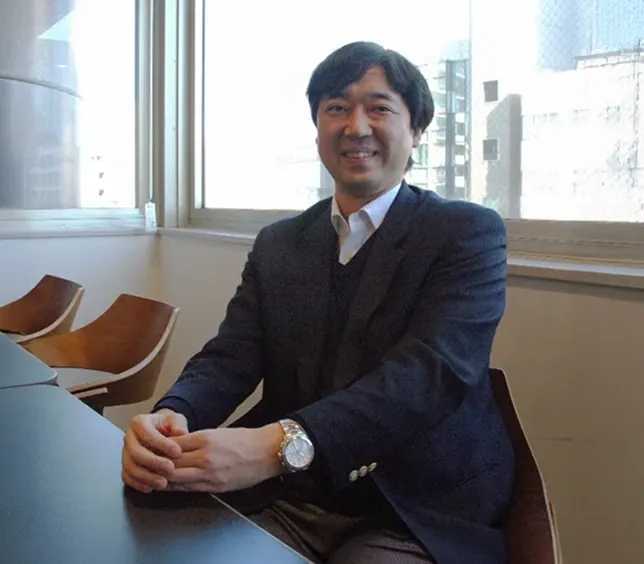
クラフトバンク総研 編集長 佐藤 和彦
大学在学時よりフリーライターとして活動し、経済誌や建設・不動産の専門新聞社などに勤務。ゼネコンや一級建築士事務所、商社、建設ベンチャー、スタートアップ、不動産テックなど、累計1700社以上の取材経験を持つ。
2022年よりクラフトバンクに参画し、クラフトバンク総研の編集長に就任。企画立案や取材執筆、編集などを担当。現在は全国の建設会社の取材記事を担当。









