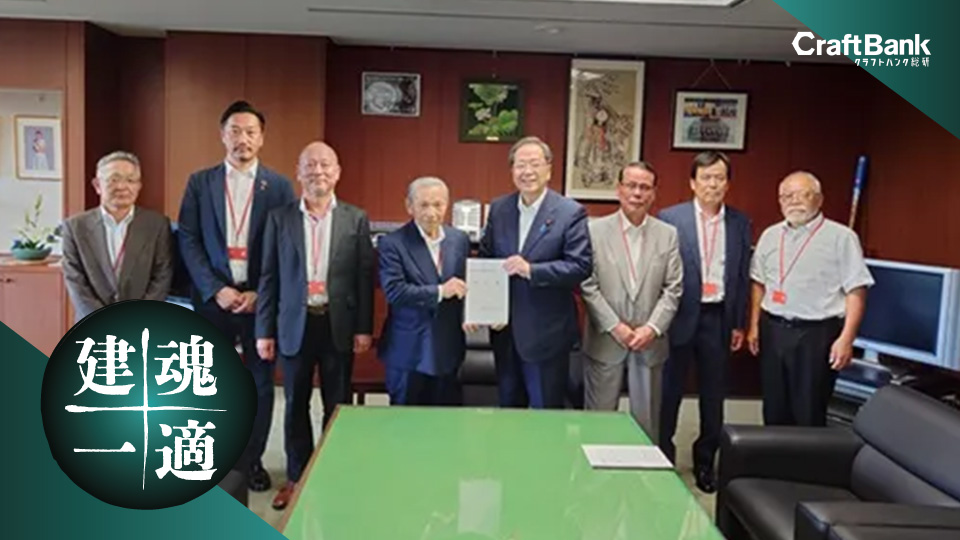広島県建設業協会連合会
更新日:2025/6/2

【低入札価格調査制度を導入して】
昨年9月に広島県が低入札価格調査制度「変動型調査基準価格」を導入した。新制度の適用後は、調査基準価格が従来の90%から下限を82%に引き下げられ、現実として下限値に近い入札が頻発している。これに伴い、安定的な利益の確保が見込めない各企業では、担い手確保に向けた週休2日や賃上げ、ICT導入など、働き方改革への対応に必須な様々な対応が、大幅に遅れる形となっている。今年7月には一部の見直しが行われ、応札者が5社未満の場合は入札価格の平均額の概ね95%、応札者5社以上は入札価格の平均額から標準偏差を引く仕組みに改正した。しかし、広島県建設業協会連合会の空久保求会長は、「このような状況が続くと、売り上げ・利益の維持が困難になると判断した企業の中には、倒産・廃業を選択肢に入れる会社が増えていく」と警鐘を鳴らす。「近年、広島県で事業継続を断念する建設会社は、現場で作業する直営部隊を抱える企業が主流となっている。これは県内で甚大な天変地異が発生した際、即座に救出に向かえる企業が皆無になることを意味する。県民の生命・財産を守るため、また最悪の事態を回避するため、当会では予定価格の90%以上を調査基準価格とする基準が採用されるよう、引き続き県に対して要望を続けていく」と強く主張する。全国中小建設業協会では、国土交通省に最低制限価格を予定価格の95%まで引き上げてほしいと要望している。全国の流れに逆行している現況を、県側はどのように軌道修正を実施していくか重要な局面を迎えている。
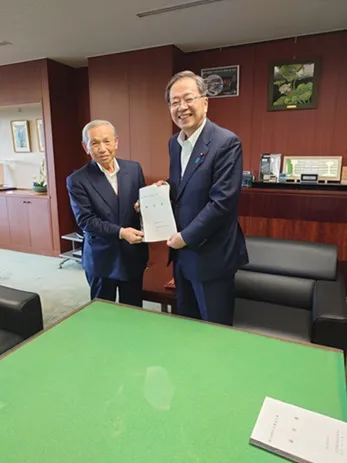
【必要となる「真」の働き方改革】
空久保会長は、「働き方改革の推進は、建設業界を魅力的に変えていくには避けては通れない道だ」と断言する。しかし、「当会の会員も含め、まだ県内の中小建設企業には日給で働く現場作業者が多く居るという現実も留意してほしい」と思いを述べる。4月からは残業時間・上限規制罰則化も開始した。これにより、日給で働く作業者には労働時間の制限がかかり、工期の延長も続出。結果的に企業の売り上げが落ちることで、労働者の収入が大幅に減り、現場で働く張本人から「前の制度に戻せ!」との声が上がる悪循環が多発している。空久保会長も「『働き方改革の実現』という掲げた目標に異論はない。だが昨年9月以降、現場からの声は日に日に凄惨な悲鳴に変わり続けている。現在もギリギリの状態で経営を続ける建設会社は多い。様々な規制が増す中で理想を具現化していくには限界を迎えており、これらの状況を加味した積算からの見直しが必要な時期に差し迫っている」と語気を強める。連合会の会員は、市町村関係の工事を直営として対応する企業が大半である。会員の雇用を守るため、また万が一に備えた体制を早急に再構築するには、どのような対応が必要になのかは明白である。

【顕著な若手の技術者不足】
今年6月に広島県土木施工管理技士会は、県内13支部の年代別会員数を発表した。全体の会員数が3504人だが、30代以下は428人、50代以上は2197人と極端な年齢構成となっていることが分かった。特に中山間部や島しょぶに当たる地域では若手技術者の不足が顕著で、このままでは近い将来は公共工事のスムーズな遂行が困難に陥ることが明らかになった。2018年の西日本豪雨災害では、河川の氾濫や浸水害、土砂災害などが発生し、広島県内では115人の尊い命を失った。空久保会長が「もう一度、2018年規模の災害が起こった場合、現時点では当時と同じような、迅速な復旧・復興工事に当たる体力が残っている会社は少ないと言わざるを得ない」と見立てを語る。行政の使命は、「安全・安心な社会・地域を守るためのハード・ソフト面の基盤を形成すること」。非常事態を迎えた後の活動に支障の出ることがないよう、広い視野で先を見据えた転換が必要となっている。

【地域の守り手としての役割】
地域建設業者の役割を空久保会長は、「地域住民の安全・安心を守りながら、地域社会の発展を目指すこと」と断言する。これらを安定的に実施していくには、担い手の確保が必須となっており、「業界全体に新3K(給与が良い・休暇が取れる・希望が持てる)を徐々にでも浸透させなければ、改善に向かうことは難しい」と捉えている。新規入職者を迎え入れるため、最近では小・中学生とその親世代へのPRにも力を入れており、特に子供の進路決定に影響の強い母親に対して魅力が伝わるよう努力する。10月19日に広島マリーナポップ(広島市西区)で開催した「ひろしま建設フェア2024」でも、かつてない程の人々が来場し、建設業が実生活の維持に不可欠な存在という点や、人々から感謝を受ける業種という点などを、イベントを通じてアピールできたという。空久保会長も建設業の醍醐味を「自分で作ったものが後世まで残り、住民の方々に日常的に使って頂ける喜びは何物にも代えられない」と語る通り、地域の守り手として確固たるプライドを持ちながら仕事に取り組み続けていることは容易に理解できる。

【可能性の模索に全力を尽くす】
空久保会長は「元請け、専門工事業者、スーパーゼネコン、発注官庁のそれぞれで考え方は違うが、『建設業を何とかしなければならない』という危機感は共通のはずだ」と力を込める。それを前提とした上で、「早急に建設業界を若い人が希望を持てる産業に変え、将来に渡って地域の安全・安心を確保できるよう、課題解決に向けた取り組みを加速しなければならない。これらの実現には、立場の違う全ての責任者がコミュニケーションの機会を頻繁に持ち、同じ方向を見た議論を一致団結で進めていくべきである」と持論を示す。不断の努力は続けてきた。しかし、民間企業の経営者・労働者を最優先に考えられなかった制度設計に、心が折れる寸前の会社も増えてきているようだ。空久保会長は、「建設業を持続可能かつ魅力的に変えるには、今後2~3年が勝負になるはずだ。他産業以上の給与水準、週休2日の確保、DXによる生産性の向上など、建設業界で働く人の待遇改善を進めるため、当会はあらゆる手段を想定した可能性の模索を続けていく」と展望を述べた。この先、広島県は発注官庁の入札・契約制度と積算方法を、どのように変えていくのか。我々はこの一点を注視し、事態の推移を見守る必要がある。
広島県建設業協会連合会のホームページ:https://www.hirokenkyou.jp/
広島県土木施工管理技士会のホームページ:https://www.hirokenkyou.jp/gishi/
この記事を書いた人
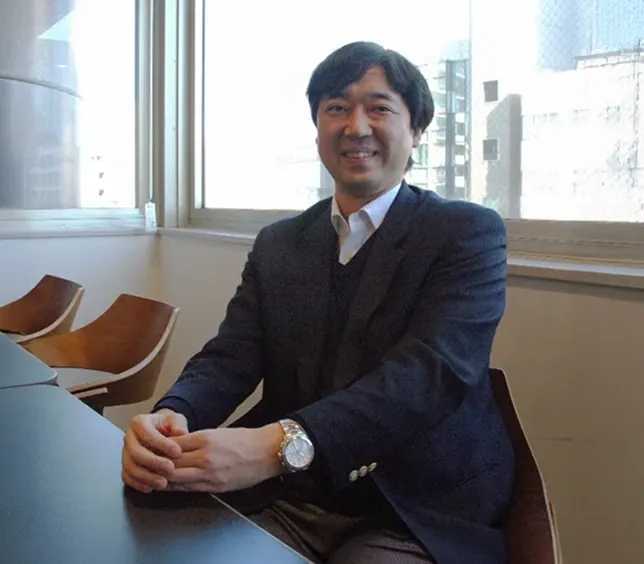
クラフトバンク総研 編集長 佐藤 和彦
大学在学時よりフリーライターとして活動し、経済誌や建設・不動産の専門新聞社などに勤務。ゼネコンや一級建築士事務所、商社、建設ベンチャー、スタートアップ、不動産テックなど、累計1700社以上の取材経験を持つ。
2022年よりクラフトバンクに参画し、クラフトバンク総研の編集長に就任。企画立案や取材執筆、編集などを担当。現在は全国の建設会社の取材記事を担当。