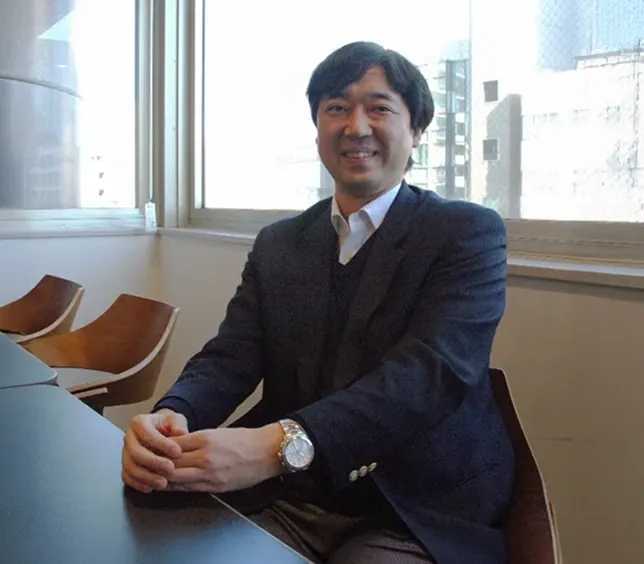国土交通省・全国仮設安全事業協同組合
更新日:2025/6/2


【安全・公平公正を最優先事項に】
建設業界での処遇改善や働き方改革、生産性向上を実現するためには、官民が連携した適切な活動が必須である。建設業では常に「地域の守り手」としての持続的な役割が求められるが、専門工事業者の賃金引き上げや、若者の担い手確保など、現状では課題が山積する。2024年4月からは、時間外労働の罰則付き上限規制の適用が開始し、これまでにない状況下での業務遂行が必要となった。しかし、現実では他産業より賃金が低く就労時間も長い上に、資材高騰分の転嫁が進まず、労務費の圧迫も続いている。今回は、国土交通省の不動産・建設経済局の職員と、全国仮設安全事業協同組合(ACCESS)・青年部会の若手経営者が、業界改善に向けた具体策を共有する座談会を実施。冒頭、小岸昭義会長が「私たち足場施工会社は、常に命の危険に直面しているにも関わらず、いまだに未払いなど元請から不当な扱いを受ける現実がある。このような現状を克服し、若者から魅力的な産業と見直されるためにも、本日のような機会を有意義に活かしたい」と挨拶。松田室長も「安全・公平公正に対する意識は、1丁目+1番地であるべき。国交省としても現場からの課題を熟知することで、新たな仕組み化に着手し、官民一体での取り組みに全力を尽くしたい」と応え、意見交換が始まった。

【新たな商慣行を見出すために】
2024年6月の建設業法改正にて、請負代金等の変更方法を契約書の法定記載事項として明確化するとともに、資材高騰などが顕在化した場合、契約前に通知をした受注者は、注文者に請負代金などの変更協議ができる規定が追加された。これにより、資材高騰分の転嫁協議が円滑化するとともに、労務費へのしわ寄せ防止が期待される。改正に至った経緯と今後の意欲的な取り組みについて、松田室長は「担い手確保のためには、処遇改善の前提となる公平な価格交渉のできる環境の整備が重要であり、新たなルールの策定に至った」と語る。「この制度は昨年12月13日に施行されているが、新しい仕組みであるため、業界全体に浸透し、しっかりと周知徹底を図っていきたい」と意欲を示す。小岸会長も「資材高騰分の転嫁協議が円滑化し、労務費へのしわ寄せ防止に繋がる法律が動くことは意義深い。現場で出る課題が改善するよう協力に徹したい」協力する姿勢を示した。

【建設Gメンの枠組み強化】
昨年の改正建設業法が公布され、技能労働者の賃金原資である労務費の確保と、その行き渡りを実現するための新たなルールが整備された。これに伴い国土交通省では、北海道開発局や地方整備局の職員をメンバーにする、建設Gメンの体制を強化。建設工事の取引において、適正な請負代金・工期設定・価格転嫁・下請代金の支払いを契約締結するため、取引状況の監視などを進化させている。特に2024年度からGメンとなる人員を72名から135名に拡大。実地調査では、発注者・元請・協力会社に対し、新しい決まりに則ったヒアリングを実施し、不当な取引の改善に努めている。鉞勇貴幹事(鉞組・代表取締役)は、「元請と専門工事会社の関係性では、当初の内訳書で提示した金額と、最終妥結し取り交わされた請け負う契約書の金額が、10%を上回る一方的な指値発注を受けることが今なお多い。これは明らかに建設業法第19条第1項・3項、第20条第3項違反しているのではないか。このような現実を踏まえ、建設Gメンの調査項目には、契約終了後の書類だけでなく、契約に至る過程も調査項目に加えて頂けると、よりクリアな環境を築けるはず」と提起。家久耒課長補佐は、建設Gメンの体制を随時改善していくことを前提の上で、「今回の改正により、指し値などの注文者による減額行為と、ダンピングといった受注者による廉売行為がそれぞれ規制されることになるため、Gメンでは、受注者による見積書の提示、受発注者間での価格交渉、契約金額の合意・契約という一連の契約プロセスを確認し、減額行為・廉売行為の有無、金額の妥当性等をチェックしていく。法令違反疑義情報などを端緒に効果的に実施していくことで、専門工事会社の適正な労務費等を確保できる枠組みを強める」との考えを述べた。法令違反の通報窓口である「駆け込みホットライン」の存在を引き続き周知すると共に、通報者が非通報者に特定され不利益を受けないよう、引き続き通報者の保護し、法令遵守に努めることにも合意した。

【安全衛生経費の適切な支払いを】
2017年3月に「建設工事従事者の安全および健康の確保の推進に関する法律」が施行された。国交省は、翌年6月に「実務者検討会」を設置。これに伴い安全衛生経費の範囲や下請まで確実に支払いが行われるための仕組み作り、民間発注者に理解を得るための具体策などが協議されてきた。江幡良太幹事(東秀興業・代表取締役)は、「足場の設計金額が、どの項目に該当するか不明瞭で、元請は変更工事に対して『設計内訳に計上されていないこと』を理由に、支払いが実施されない現実がある」と指摘。特に仮設工事では、当初設計と実際の現場との乖離が激しく、設計業務の段階で仮設計画を専門工事業者に分離発注するなどの指導も求めた。これを受け入交企画専門官は、「現時点では統一した見解を示すことは難しい」とした上で、「重要なのは、必要な安全衛生対策が実施されることであり、元請・下請のどちらが実施し、費用負担するのかを、その都度確認する必要がある」と回答。まずは、安全衛生対策項目の確認表と標準見積書の取り組みを進めることで、経費の適切な支払いにつなげていくことを示した。また、仮設設計に関しては、「公共工事においては、当初設計時と現場条件が異なる場合には、設計変更の対象となるので、設計条件の確認をお願いしたい」と回答。ACCESSによれば、橋梁経費では初期段階での設計から80%近くも隔たりが出ることも珍しくなく、その大部分を無償で下請が請け負い続けている現実もある。このような事態を減少させるための具体策は急務である。

【見える化・意識改革・フォローアップ】
これまで国交省では、法定福利費・安全衛生経費・建退共掛金を必要経費と捉え、安全衛生経費を内訳明示する「標準見積書」の浸透に尽力してきた。ACCESSでもその策定作業に携わり、徐々に適切かつ明確な支払いに繋げられるよう双方で努めてきた過程がある。2022年6月からは本件でもWGを設置し、適切な安全衛生経費を支払うための施策を推進している。千田英治幹事(エイチ・専務取締役)は、安全衛生経費が下請け契約上の「必要経費」と位置づけようとする取り組みに感謝を示しつつ、今後の見直しについての質問を出すと、松田室長は「中央建設業審議会に設置された労務費の基準に関するワーキンググループ(WG)においても、労務費と合わせて確保すべき必要経費として議論されている。安全衛生経費の確保に向けた更なる取組を進めたい」と返答し、安全衛生経費の実態に関する調査や、標準見積書の事例などをホームページなどで公開することに意欲を見せた。適切な労務費の確保に向けた新たなルール化に組み込むなど、安全衛生経費に関しては、見える化・意識改革・適切な支払いに向けたフォローアップがポイントであり、全国安全週間などを活用した集中的な広報活動も重要な役割を果たすことが予想される。

【賃上げによる処遇改善の実現】
改正建設業法においては、賃上げの原資となる労務費の適切な支払いに向けた「労務費の基準」を中央建設業審議会が作成・勧告し、これを目安にしながら、労務費等を内訳明示した見積書で価格交渉する仕組みが設けられた(本制度の施行は本年末目処)。中央建設業審議会の労務費に関するWGにおいて、労務費の基準の制度設計について議論が進んでいるが、大仲孝明副会長(太洋リース・代表取締役)からは、「足場は形に残らないため、『事故さえ起らなければ良い』と軽視される傾向が強い印象を受ける。しかし、専門工事会社が、適切な単価・人数、安全な機材、着実な運搬など、物事を遂行する際は、あらゆる物事に金銭を含めた費用が発生する現実も認識し、今後も標準労務単価の見直しを検討してほしい」と要望を出した。松田室長は「これまで4回のWGを開催しており、最終的には賃上げによる処遇改善の実現を目指している。公共・民間、元請・下請など範囲を限定させず、全ての領域で設計労務単価を基軸にした適正水準の労務費の確保が重要と認識している」と説明。WGを運営する中で重点を置く項目に関しては、「実効性を担保するための措置」を挙げ、労務費・必要経費などを明示した見積書の提出や、建設Gメンなどを機能させながら新たな商慣行を定着させていく方針を伝えた。

【12月の施行に全力を尽くす】
松田室長は標準労務費について、「技能者の方を最優先にした、新しい商慣行を官民が一体となって構築していきたい」と意気込みを見せる。実際に制度を走らせてみると、当初では想定外だった事態が発生する可能性もある。しかし、完璧でなくても、まずはこれまでにない構造を基にスタートを切り、最前線で表面化した課題を抽出することで、臨機応変に修正できる体制を掲げられる意味は大きい。新たな試みの開始時期は、2025年12月だ。施行までの期間はわずかだが、専門工事会社からの信頼を獲得するため、取り組むべき懸案事項は依然として残されているはずである。