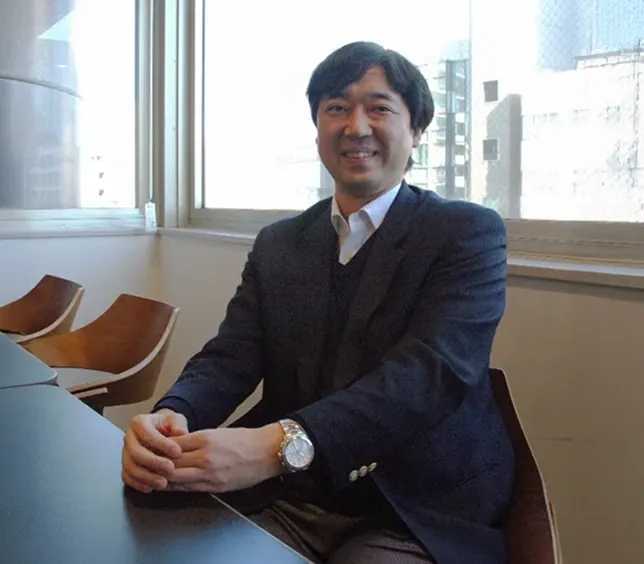日本港湾空港建設協会・静岡県支部 全日本漁港建設協会・静岡県支部
更新日:2025/11/5
【「港湾」・「漁港」を浸透させるために】
日本港湾空港建設協会・静岡県支部と全日本漁港建設協会・静岡県支部にて、支部長を務める佐野茂樹氏(青木建設・代表取締役)は、「港湾・漁港の仕事が、一般の方に認知されるには何をすべきか?」を常日頃から考えている。海上物流やクルーズ船のことや、国民に安全・安心な水産物の安定供給を図る基盤として、海岸線に有する漁港・漁場の整備に携わる重大な任務。2008年の支部長就任以降、様々な専門的なアプローチを続けてきたが、「重要なことは地場に根差す住民の方々に、『港湾』・『漁港』という存在を知って頂くための周知活だった」との意向を改めて示す。協会として掲げる理念は、「地域に愛される夢と誇りある港湾・漁港建設業」。安定かつ魅力的な事業活動ができる環境づくりを目指し、幅広い活動を新たに実施する姿勢を見せている。

【予算確保と作業船舶の利用】
支部の活動としては、港湾・漁港建設に従事するため、近年多発・大規模化する災害から地域を守る役割もあるが、佐野支部長は「最も重視していることは、予算を確保することと、作業船舶を使う状況を生み出すこと」と明言。昨今の物価高騰の影響により、例年通りの予算維持だとコストが増え、実質ではマイナス状態に陥ること。また、港湾・航路など底面の土砂を取り除く浚渫工事を維持するには、日頃から作業船を稼働させるが必須であることに触れ、「課題は山積みだがインフラ整備の実現には、一定以上の予算確保が必須という現実も定着させたい」との考えを述べる。事前防災の観点からも、様々な箇所で防波堤の増設は要になる。部署内に設置している技術委員会や意見交換会なども活かし、更なる改善・改良に意欲を見せている。

【地域に身近な環境を提供する】
「港湾」・「漁港」の認知度を普及する上で、佐野支部長は「家族でくつろげる空間を作るなど、地域の方々がなじめる環境の提供が先決だ」と思いを寄せる。徐々にでも立ち入り禁止の区域を緩和することや、プレジャーボートの利用も推奨するなど、「レジャー施設としての活用も検討することで、地域との距離を徐々にでも縮めていくべき」との考えも提示する。熱海港では、国土交通省が主導する形で防波堤を海釣り場として開放し、観光客を中心に海岸方面に向かう人々を増やすことに成功している。まずは「船を利用して旅行してみよう」「海を遊び場にしよう」という身近なメッセージを送ることでも構わない。近年では、港を核とした街づくりを目指す「みなとオアシス」や、地元で親しまれた水産物を活かした料理を薦める「Sea級グルメ」が全国で親しまれているように、「官民一体となった連携を増やすことで、各地を盛り立てていきたい」と並々ならぬ思いを全面に出している。

【港湾・漁港建設業の健全な維持発展を】
日本の沿岸には、国際戦略港湾をはじめとする930もの港湾と、大小合わせて約2800ヶ所の漁港が存在する。各地の岸壁・物揚場、船揚場、航路などを維持管理するには、熟練した技術や人材の育成・伝承が必要であり、佐野支部長は「これら全ての課題に対応するには、やはり日頃から安定的な仕事を確保し、非常事でも即座に動き出せる体制を完備しておくことが不可欠」とポイントを述べる。これまで慣習として継続してきた事柄も多く、「これらの壁を崩すことも当支部の使命」と覚悟を見せる。支部の役割としては、海浜や港湾・漁港地域の清掃、古くから続く祭りやイベントの支援、体験学習の開催など多岐に渡るが、「団体活動と各地域との連携は欠かせない業務。この部分を疎かにすることなく、バランスを重視した最善策に取り組みたい」と明確なスタンスを示す。「港湾・漁港建設業の健全な維持発展に努めていく」。佐野支部長の目線は常に前だけを見つめており、今後も堅実かつ成長を前提とした団体運営で、業界を牽引していく方針である。
この記事を書いた人

クラフトバンク総研 記者 松本雄一
新卒で建通新聞社に入社し、沼津支局に7年間勤務。
在籍時は各自治体や建設関連団体、地場ゼネコンなどを担当し、多くのインタビュー取材を実施。
その後、教育ベンチャーや自動車業界のメディアで広告営業・記者を経験。
2025年にクラフトバンクに参画し、記者として全国の建設会社を取材する。