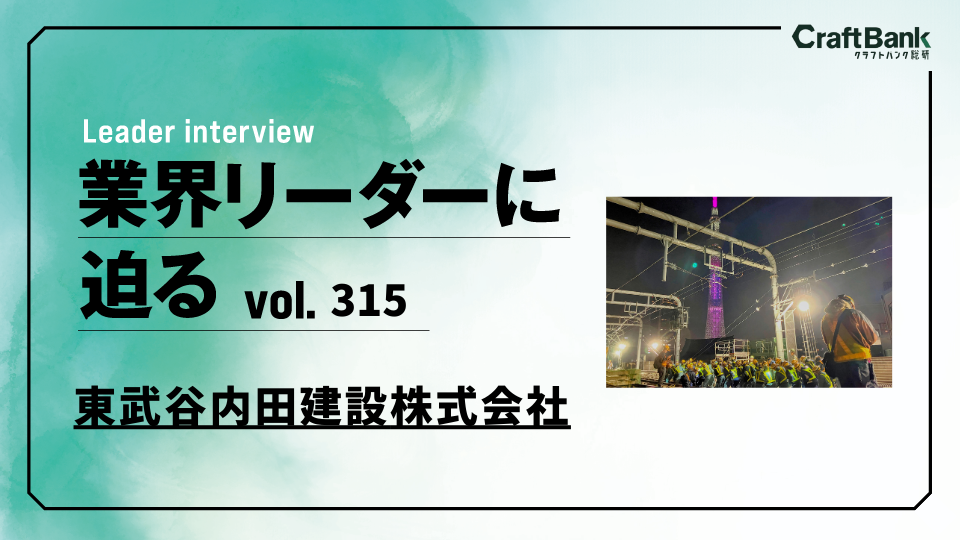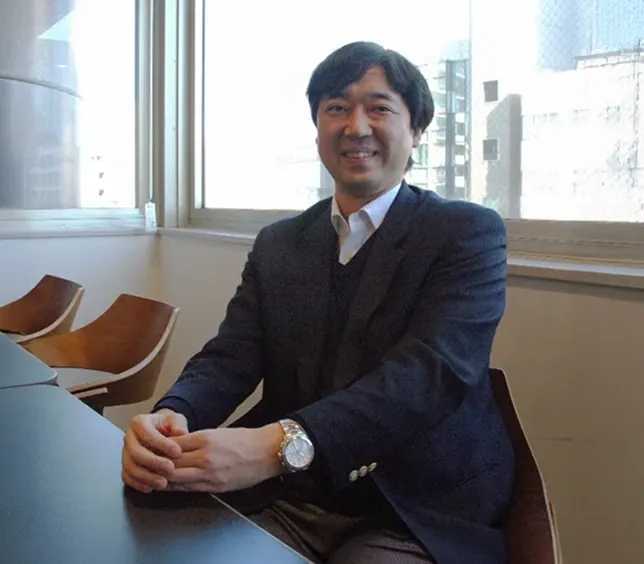「建設業界に光を当てる」 編集長・佐藤が見据えるクラフトバンク総研の目的地
更新日:2025/4/29
クラフトバンク総研の編集長・佐藤和彦が、入社して1年半が経過する。大学在学中からフリーライターとして活動を始め、経済誌や新聞社の記者を経て、2022年9月にクラフトバンクに参画。クラフトバンク総研内に、「業界リーダーに迫る」や「我が社の突破者」、「建設業界トレンド」などのコーナーを創設し、建設業界で働く企業や人々の魅力を発信している。今回は、「業界リーダーに迫る」の連載100回目を記念して、編集長・佐藤にクラフトバンク総研メディアの立ち上げや今後の展望などを聞いた。(聞き手=韓英志・クラフトバンク代表取締役社長、記事作成者=川村智子・クラフトバンク総研記者)
―クラフトバンクに入社を決めた経緯を聞きたい。
「前職・建通新聞社の退職を決意した際、以前から上場企業など複数からスカウトを頂いていたので、その時点ではその中の1社にお世話になる予定だった。しかし、クラフトバンクに対しては、記者活動の中で代表の韓を含め多くの社員と良好な関係を築けていたので、22年6月の取材時点で、事前に退職の意向とこれまでの感謝を伝えた。すると、血相を変えた韓から『当社からも提案がある。話だけでも聞く時間を取ってほしい』と申し出があったので、別日に会合の場を設けることにした。当日は、韓と当時28歳だった共同創業者・事業責任者の田久保彰太から、クラフトバンクの現況や課題、事業展望などに関する渾身のプレゼンテーションを受け、徐々に転職先を変更する方向に気持ちが傾き始めた。

―入社の決め手を教えてほしい。
「田久保を筆頭に、創業メンバーが桁外れに有能だったこと。また、建設業に特化した経営管理システム『クラフトバンクオフィス』の特徴を知れたことが最大の要因だ。これまで前身のユニオンテック時代から何度も取材はしてきたが、個人的には韓の剛腕で会社内の全てを取り仕切っていると勝手に捉えていた。しかし、田久保や営業責任者・神山巧などの底知れぬ力を知るにつれ、『クラフトバンクは、各部署に極めて優秀な人材が配置された組織。そこで私にしかできない色を加えられたら、これまでにない景色が見られる』と確信したことが決め手となった。

―クラフトバンクオフィスの魅力を聞きたい。
「建設企業がDXでバックオフィス業務の負担を軽減し、工事業に専念できる環境を提供するだけでなく、当社から担当者が1人付き、活用のサポートや経営面のアドバイスまで行うことで、導入企業と伴走できる仕組みが魅力的と感じた。特に新聞社に在籍時、現在カスタマーサクセス(CS)を統括する前田紘人を取材した際、大成建設というスーパーゼネコンからの転身や、その合理的かつ柔軟な思考・発想力を目の当たりにし、『このようなメンバーが集結し事業を展開すれば、建設業界の変革に繋がっていく』という兆しが見えた。私は、再三メディア側から『DX化を早急に実施しなければ、建設業界全体が沈む日も遠くない』と訴え続けたが、業界内のリアクションは皆無に等しく、専門新聞という媒体の無力さを日々痛感していた。当社の社員やクラフトバンクオフィスを知り、『建設業界を変えるのは、新聞社でなくクラフトバンク』と信じ切れたことが全ての始まりだった。

―入社後の取り組みを聞きたい。
「会社側からは、『メディア人としての経験を活かし、日本が世界に誇る建設業界を盛り立てる手法を考え、記者活動を通じてその具現化を進めてほしい』と通達を受けたのみだった。私には、大学在学中からライターとして活動し、様々な業界の経営者・社員の魅力を照射し続けた経験がある。すぐに『建設業界で活躍する人・企業に光を当てること』をコンセプトに、ウェブ上で『業界リーダーに迫る』を立ち上げ活動を開始した。懸念点は取り組みの認知度が普及するまで、ある程度の時間を要することだったが、韓と田久保からは『僕たちの確認は必要ないので、長期的な視点に立ち、好きなように思う存分やり切ってほしい』と全幅の信頼を寄せられていた。プレッシャーは大きかったが、この言葉を羅針盤に『この活路は自力で切り拓くしかない』と覚悟を決め、トライ&エラーの繰り返しを経てコーナーの継続・浸透に尽力した」

―活動を続ける上で苦労した点は。
「初期段階では、noteでの発信しかなかったこと。そして知名度も掲載例も少なかったので、懸命にコンセプトや見立てを説明しても、『気持ちは伝わったが、具体的なイメージが湧かず、メリットもなさそうだから見送る』という返答が続出したことだ。『0→1の過程では、避けては通れない道』と理解しつつも、打開策の模索に苦慮した現実はあった。突破口となったのは、過去に取材した多くの経営者から『佐藤くんが困っているなら、何でも引き受けるよ』と温かく迎えて頂けるケースが急増したこと。この時ほど、私は『様々な方のサポートにより、今なお生き続けられている』と実感した経験はなく、月並みだが感謝の気持ちを忘れず日々を過ごす重要性を再認識した。また、当社の社員からの薦めにより、旧Twitterで個人アカウントを開設し、全国の建設企業の方々と関わりを持てたことも局面転換に繋がった。各地には、独自の経営手法で組織を動かす優秀な経営者が多く居て、現地に赴いて詳細な情報交換ができたことも、前職では成し得なかった変化である」
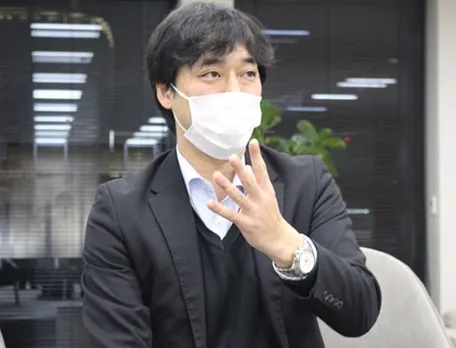
―建設業の醍醐味とは。
「多くの企業や人々が現場で団結し、各々の知識・技術を共有し合って、1つのモノ作りに邁進できる点が何よりの醍醐味だ。これまで何度も建設現場を取材してきたが、安全かつ高品質な施工や独自開発した工法、アクシデントへの対応など瞬時に実施する職人への尊敬の念が、今日まで途絶えたことはない。現場では『真の意味で、私たちのような専門工事業者に重点を置いたメディアがない』という貴重な意見も聞くことができた。クラフトバンク総研では、このようなマクロ・ミクロ双方の視点を併せ持った、ポジティブな独自情報が提供できるよう、『現場の声』を最優先にした取材活動を継続する」

―今後、どのような組織運営を想定しているのか。
「この1年半で各コーナーを定着させることはでき、メディアとしての力もついてきた。今後は、編集長として新たな可能性を追求すると共に、同じ部署に所属する記者の経験値を飛躍的に上げたい。具体的には、これまで私が担ってきた全ての業務を、各記者が滞りなく行えるようフォローし、極論すると私が不在でも何事もなく回る組織を確立する方針だ。建設業界は旧態依然としており、あらゆる対応が遅過ぎると言われ久しい。しかし、それは裏を返せば変化に対する伸び代が大きいということ。残業上限規制の罰則化が近々に迫るなど、切迫した多くの壁が立ち塞がる現実はある。このような現状を打破するためにも、クラフトバンク総研内では、全国で活躍する企業・人・団体の魅力にフォーカスした情報を発信し、業界全体のバックアップに全力を尽くしたい」

この記事を書いた人

クラフトバンク総研 記者 川村 智子
新卒で入社した建設コンサルタントで、農地における経済効果の算定やBCP策定などに従事。
建設業の動向や他社の取り組みなどに興味を持ち、建通新聞社では都庁と23区を担当する。
在籍時は、各行政の特徴や課題に関する情報発信に携わる。2024年よりクラフトバンクに参画。
記者として企画立案や取材執筆などを手掛けている。