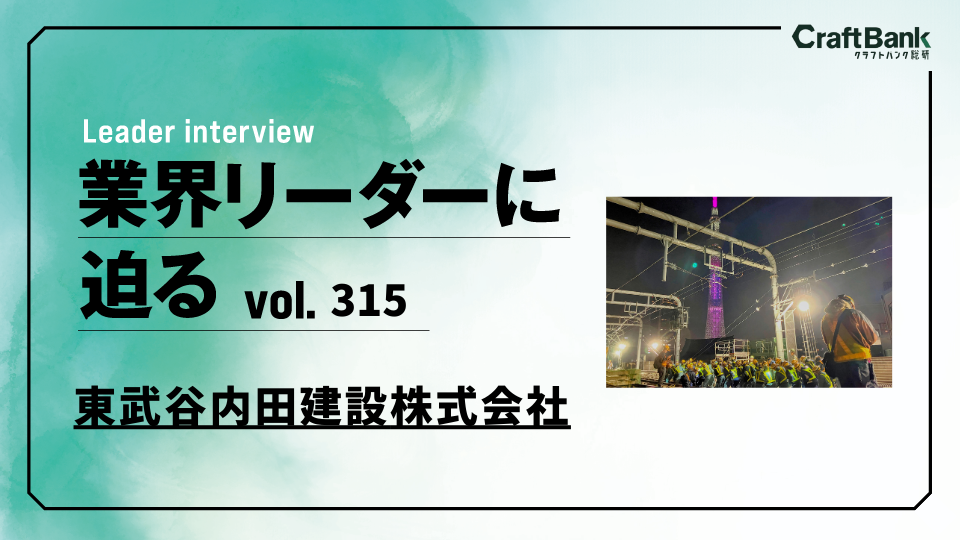大工の会が潜在能力の拡張を図る
更新日:2025/5/2
2022年に大工の根本を見直し解決を目指す「大工の会」が発足した。代表を務めるのは、木村建造株式会社(千葉市稲毛区)の木村光行棟梁。大工の間口を広げることで、入職希望者を増やすことを目的に設立した。当初、InstagramやFacebook、LINEなどSNSを駆使して集めていたメンバーは、新築・リフォーム大工の垣根を越えて現在は80人ほどに増加。定期的な共有会などを開催することで切磋琢磨を続けている。


大工の会では、実務的な技術指導から建設業の概要理解を含む座学、どのような形を踏めば稼げる組織を組成できるかなど、様々な情報提供を実施している。木村棟梁は、「当会では、幅広い分野の情報を取り扱うため、即効性がある訳ではないが、メンバー各々が『常識』と設定してきた概念を打破できるケースが非常に多い」と現況を話す。参加者にも高いモチベーションを維持する者から、何となく誘われて来た人など幅があるため、内容は経営・マネジメントから働く意味・成長の定義など、誰一人も取りこぼさないよう工夫した運営を心掛けている。メンバーの中には、習得した技術・知識を活かすことで、既に3~4倍の売り上げ実績を残す会社も出始めており、徐々に大工の会の認知度が浸透しているようだ。


木村棟梁は現在、「人材育成に力を入れている」と方針を語る。会に参加したメンバー同士が仕事を紹介し合うことで、双方の技術・経験を補完し実績に繋がることも増えてきた。最近では、「話を聞くだけでは、人工単価は上がらない」と腹落ちし、能動的に行動を起こすメンバーも現れ始めたという。「戸建てだけでなく、CLT建築や大規模木造、非住宅木造など、大工にはまだ多様な可能性が残されている。大工である以上、技術習得に向けた行動は必須。大工の会では、大工というカテゴリーをもう一度主役の舞台に押し上げられるよう、トライ&エラーを繰り返していきたい」と意気込みを語る。


木村棟梁は大工の会を「参加者にとって人生のターニングポイントになるよう、様々な試みを仕掛けていきたい」と話す。当初では想像もできないほどメンバーも増え、「最近では正直、会の規模が縮小することに対する恐怖感も抱き始めた」と本音も漏らす。現場で活きる実践的な技術と、ビジネスとしてマネタライズに繋がるノウハウの提供。鳥の目と虫の目の双方を伝授する困難さには日々苦しんでいるようで、優秀な大工が一朝一夕で生まれないことを改めて認識できる。「引き続き、大工としての限界突破が実現できるよう、会の運営に全力を尽くす。まだ道半ばの状況だが、大工には選択肢が多いことは事実。この点を忘れることなく、同じ志を持った仲間たちと大工の可能性を証明していきたい」。


この記事を書いた人
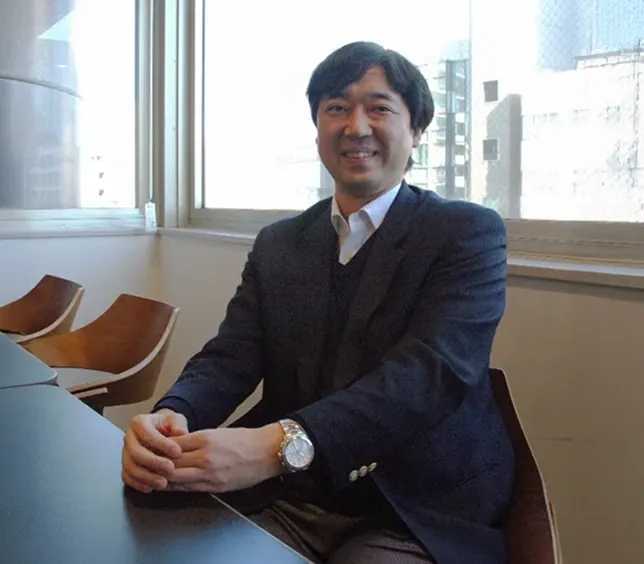
クラフトバンク総研 編集長 佐藤 和彦
大学在学時よりフリーライターとして活動し、経済誌や建設・不動産の専門新聞社などに勤務。ゼネコンや一級建築士事務所、商社、建設ベンチャー、スタートアップ、不動産テックなど、累計1700社以上の取材経験を持つ。
2022年よりクラフトバンクに参画し、クラフトバンク総研の編集長に就任。企画立案や取材執筆、編集などを担当。現在は全国の建設会社の取材記事を担当。