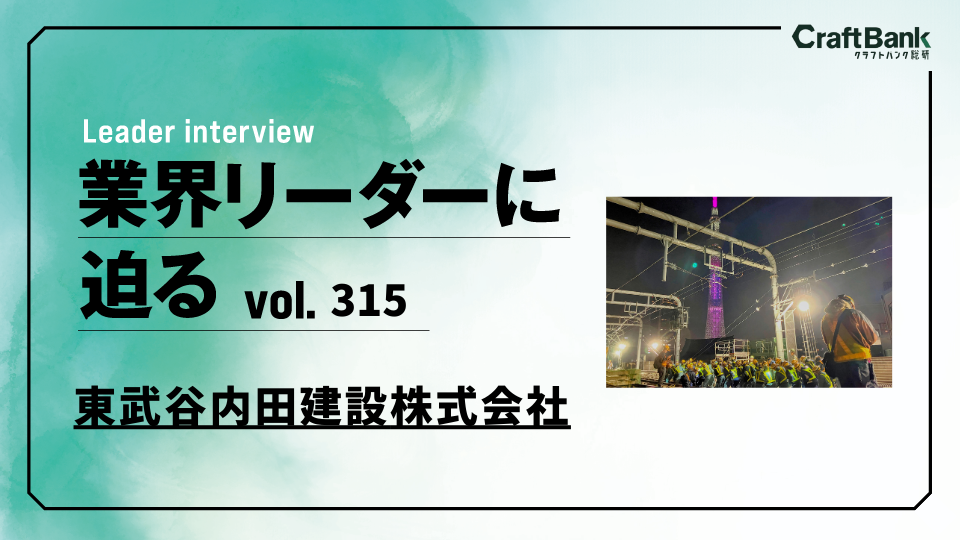地域社会の安定に向けた模索を継続 栃木県アスファルト合材協会
更新日:2025/4/10
栃木県アスファルト合材協会の磯部尚士会長が、来年5月に5期目の任期を終える。これまで明確なルールではないが、「会長は、最低でも5期・10年の期間を全うすること」という不文律を意識してきており、「その後の予定はまだ決めていないが、今は任期終了まで全力を尽くすことだけを考えている」と意欲を見せる。最優先事項は、「現状維持に努めること」。先行きが不透明な時代に突入しているが、今ある状態を保つための暗中模索は続きそうだ。


川上清副会長は、「栃木県でのアスファルト合材の年間出荷量は、90年代の150万㌧をピークに年々減り続け、現在は約70万㌧で終始しているのが現実。最盛期に戻すことは難しいが、実績に基づき地域に根差した企業の雇用が守れるよう、出荷量の増加に向けた活動をする」と固い意志を示す。栃木県の地場ゼネコンでプラントを所有する企業は6社ほどに減少している。他県と違い大手企業とのJVは組まない方式を採用してきたが、磯部会長は「このままだとJVを取り入れざるを得ない状態になる」と現状を語る。外的要因による資材高騰など厳しい状況下での事業継続は、赤字覚悟を強いられる。自社だけで設備投資を実施するにも莫大な費用が掛かる。「万が一の発生時に備えたい」との協会の思いと現実には乖離があり、その板挟みに苦しまされているようだ。


協会では現在、国が示す指針に従いCO2排出量削減の取り組みへの着手も検討する。具体的には、アスファルト合材の製造温度を低減するなど、低炭素から脱炭素社会への挑戦を検討しており、製造に必要な燃料消費量の削減による「低炭素アスファルト舗装」の実現にも備えている。磯部社長は、「環境と共生するアスファルト合材工場の構築にも注力し、多様化・高度化する要請を果たす準備も進めたい」と意気込みを見せる。最近では、「人工的にでも単価を上げるには、生コン業界と同様にプラント数を削減し、供給量を下げていくしか方法はないとも感じている。心苦しい点は多いが、理想と現実の間にある中庸点を探しながらの団体運営を心掛けたい」と実感を込めて語る。協会設立の目的は、各社の技術力を向上することで地域の安全・安心を確保すること。会員増加は極めて難しい状況だが、制限がある中でも協会は今も改善案を探している。

現在、栃木県のプラントは全体的にメンテナンスが必要な時期を迎えており、川上副会長は「リニューアルを実施すべきか、畳むべきかを決断する時期が近づいている」と想定する。設備投資を含め高い技術とコストが掛かることからも、「他県と同様に大手との連携も選択肢に入れる必要もあり、この数年は協会としてのターニングポイントを迎える可能性が高い」と見立てている。昨今、各地で起こり始めた悲惨な事故が顕在化した通り、万全なインフラを整備するには、相応の準備が必須であり、この部分だけは疎かにすべきではないことは明白だ。国民の生命・財産を守るため、国を含めた各行政はどのような判断を下すべきか。栃木県アスファルト合材協会は、今後も地域社会の安定に向けた活動を継続していく方針である。
関連記事:建設業界トレンド 『栃木県舗装協会などが新年賀詞交歓会』
この記事を書いた人
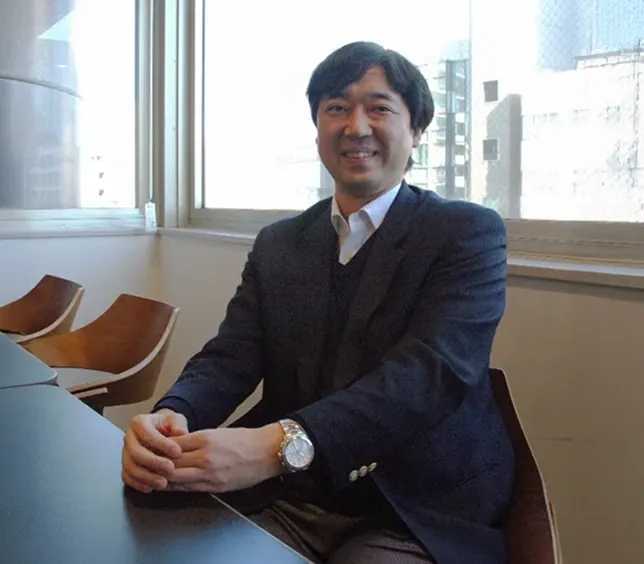
クラフトバンク総研 編集長 佐藤 和彦
大学在学時よりフリーライターとして活動し、経済誌や建設・不動産の専門新聞社などに勤務。ゼネコンや一級建築士事務所、商社、建設ベンチャー、スタートアップ、不動産テックなど、累計1700社以上の取材経験を持つ。
2022年よりクラフトバンクに参画し、クラフトバンク総研の編集長に就任。企画立案や取材執筆、編集などを担当。現在は全国の建設会社の取材記事を担当。