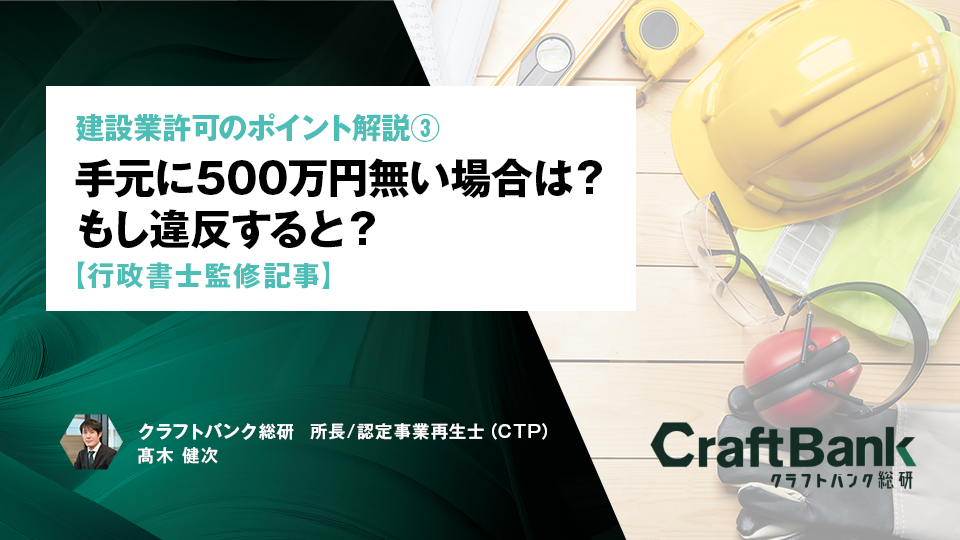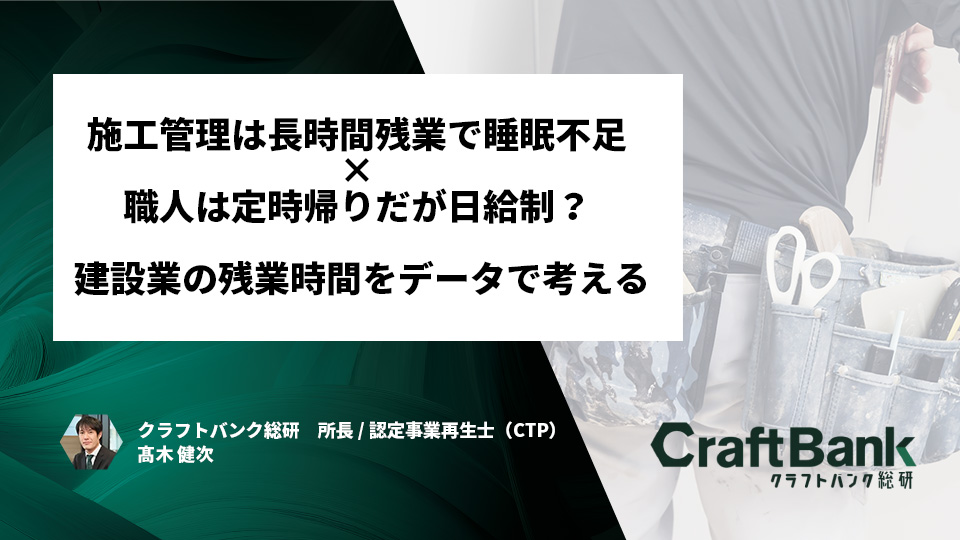手元に500万円無くても建設業許可を取得できるか? 建設業法に違反するとどうなるか?【行政書士監修記事】
更新日:2025/4/17
手元に500万円無くても、建設業許可を取得できるか?
建設業法に抜け道は無いのか? 違反するとどうなるのか?
建設業に関わる方でこういった疑問をお持ちの方向けに、行政書士の先生の監修のもと、建設業許可申請について記事を配信しています。
特に独立や建設業許可を新規取得して工事業に参入を検討される方にとっては重要な内容になっています。
建設業許可申請のポイント② 当社は建設業許可を取得できるか?【行政書士監修記事】
https://corp.craft-bank.com/cb-souken/kyokashinsei2
なお、本記事は前回に続き、行政書士法人みそら(静岡県)の代表・塩崎宏晃先生に内容を監修いただいています。
https://www.misora.or.jp/
非常に複雑な内容ですので、塩崎先生を始めとする「建設業に強い行政書士の先生」に相談されることをおすすめします。前回記事の通り、行政書士の先生でも建設業許可を取り扱っていないこともありますので、ホームページ等で建設業における実績を確認されることをおすすめします。
500万円を用意できなくても建設業許可を取得できるか?
建設業許可を取得するためには6つの条件があります。(建設業法第7条、8条、令和2年改正建設業法)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/16bt_000082.html
具体的には以下の6つです。
① 経営業務の管理責任者がいること
② 営業所ごとに専任技術者がいること
③ 請負契約に関して不正や不誠実な行為をする恐れが無いこと
④ 請負契約を履行するに足りる財産的基礎があること
⑤ 適正な社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)への加入
⑥ 欠格要件に該当しないこと
(禁固以上の刑に処せられる、労働基準法違反等で罰金刑等に処せられてから5年を経過しない者などは取得できない)
この④の財産的基礎の基準が「自己資本500万円」とされています。
建設業は資材、機材、工具の購入が必要で、それらの購入資金が必要になるので建設業許可を取得するには最低限の資金が無くてはならない、とされています。
ではこの「自己資本500万円」とは具体的にはどのような条件でしょうか? 一般建設業の許可を受ける場合を想定して記載します。
(一般建設業許可と特定建設業許可の違いはこちらhttps://corp.craft-bank.com/cb-souken/kyokashinsei1 )
一般建設業の許可を受ける場合、次のいずれかを満たす必要があります
1. 自己資本の額が500万円以上であること
2. 500万円以上の資金を調達する能力を有すること
3. 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
以下、詳しく見てみます。
1.自己資本とは?
法人の場合、貸借対照表における純資産合計の額を言います。
個人事業主の場合、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から、事業主貸勘定の額を控除した額に、負債の部に計上されている利益保留性の引当金及び準備金の額を加えた額を言います。(自己資本=銀行預金残高ではありませんので、詳細は税理士の先生にご確認ください)
この場合の確認は財務諸表で確認されます。創業間もなく、決算書の提出が困難な場合は、創業時の財務諸表にて要件を満たすか判断されます。
資本金が500万円以上ある法人の場合、最初の決算が終わるまでなら「500万円以上の財産がある」と見なされます。ただし、一期の決算が赤字の場合は逆にこの500万円の要件を満たさなくなってしまいますので注意が必要です。
2.500万円以上の資金を調達する能力とは?
担保となる不動産を保有していること等により、金融機関等から500万円以上の資金の融資を受けられる能力を言います。具体的には金融機関の預金残高証明または融資証明書等で確認します。
創業時の融資は「日本政策金融公庫」などの公的金融機関が取り扱っています。
https://www.jfc.go.jp/n/finance/sougyou/riyou/sougyouji/
金融機関の預金残高証明書、融資証明書等の取得は通常、受付から1週間以上かかるとされています。許可申請のタイミングに届いていない等の事態にならないよう、早めの準備をおすすめします。(おすすめできませんが、経営者個人のお金を一時的に持ってくる、親族から借りるなどもあるそうです)
また建設業許可の審査に際して残高証明書や融資証明書の発行日から1か月前後の有効期限を定めている都道府県が多いので、ほかの書類を整えてから最後に入手するようおすすめします。
また、金融機関から融資を受ける際に建設業許可が必要、という事例もあります。
参考:銀行は建設会社のどこを見ているか?
https://corp.craft-bank.com/cb-souken/ginnkou

建設業許可に「抜け道」「裏技」はあるか?
結論からすると「抜け道」や「裏技」はありません。
そもそも、建設業法は戦後、違法業者を取り締まるために制定され、何度も改訂されて今日に至っています。建設業許可の要件も「工事には職人の腕だけではなく、資金、資格、法律、経営の知識経験、社会保険なども必要」という主旨です。
建設会社に勤務していた普通のサラリーマンが独立後すぐに建設業許可を取得するのはハードルが高いのです。(そのため、独立するよりも転職する人が多いのです)
建設業法第3条に規定されている建設業許可が必要な工事の要件は以下の通りです。
・建築一式工事以外の工事の場合、1件の請負代金が500万円以上
・この500万円は資材費、運搬費、消費税込み
資材が元請支給の場合、その資材費も500万円に含みますので、建設業許可が不要な工事は現実的に本当に軽微なリフォーム等の工事だけ、となります。
「抜け道」として工事の大きさを「500万円以下」にするなどを考える人もいるかもしれません。しかし、本来1200万円の工事を、強引に請負契約を分け、450万円+450万円+300万円等に分けることも違法です。
建設業法第47条1項では建設業法における罰則規定が定められています。
「第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者」は「三年以下の懲役または三百万円以下の罰金に処する」となっています。
具体的には、営業停止のほか、罰金、過料、懲役、などの罰則や行政指導を受けることになります。そして、その者が建設業許可を受けようと思っても5年間は取得できなくなってしまいます。
なお、処分の実例は国交省のネガティブ情報サイトで検索閲覧可能になり、公表されます。
https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi
繰り返し無許可業者と請負契約を結んだ発注者も行政指導の対象になります。
最近はトラブルになった下請業者からの告発等もあり、そこで発覚することも多いのです。
許可を取得すると毎年許可行政庁に工事経歴書を提出します。そこに記載された工事請負金額や、配置技術者の内容から、聞き取り調査、処分に至るケースもあります。
国土交通省は現状、建設業許可が不要な500万円未満の「軽微な工事」についても住宅リフォーム工事でのトラブルの多発を踏まえ、建設業許可の対象にするもしくは何らかの規制をするとの報道もあります。「工事には建設業法などの知識と行政書士の先生との連携が不可欠」によりなっていくでしょう。
クラフトバンク総研は無料で様々な工事会社の経営に関わる情報も発信していますので、そちらもご覧ください。
関連記事:建設業許可の取得方法
https://corp.craft-bank.com/cb-souken/kyokashinsei2
監修:行政書士法人みそら(静岡県)代表・塩崎宏晃先生
日本行政書士会連合会 03171958
静岡県産業振興財団 登録専門家
建設キャリアアップシステム認定アドバイザー
参考図書
https://www.shuwasystem.co.jp/book/9784798061658.html
この記事を書いた人

クラフトバンク総研 所長 / 認定事業再生士(CTP) 髙木 健次
京都大学在学中に塗装業の家業の倒産を経験。その後、事業再生ファンドのファンドマネージャーとして計12年、建設・製造業、東日本大震災の被害を受けた企業などの再生に従事。その後、内装工事会社に端を発するスタートアップ・クラフトバンク株式会社に入社。
2019年、建設会社の経営者向けに経営に役立つデータ、事例などをわかりやすく発信する民間研究所兼オウンドメディア「クラフトバンク総研」を立ち上げ、所長に就任。
テレビの報道番組の監修・解説、メディアへの寄稿、ゼネコン安全大会、業界団体等での講演、建設会社のコンサルティングなどに従事。
・YouTube出演
「石男くんの建設チャンネル(@construction-Youtuber)」にて多数出演