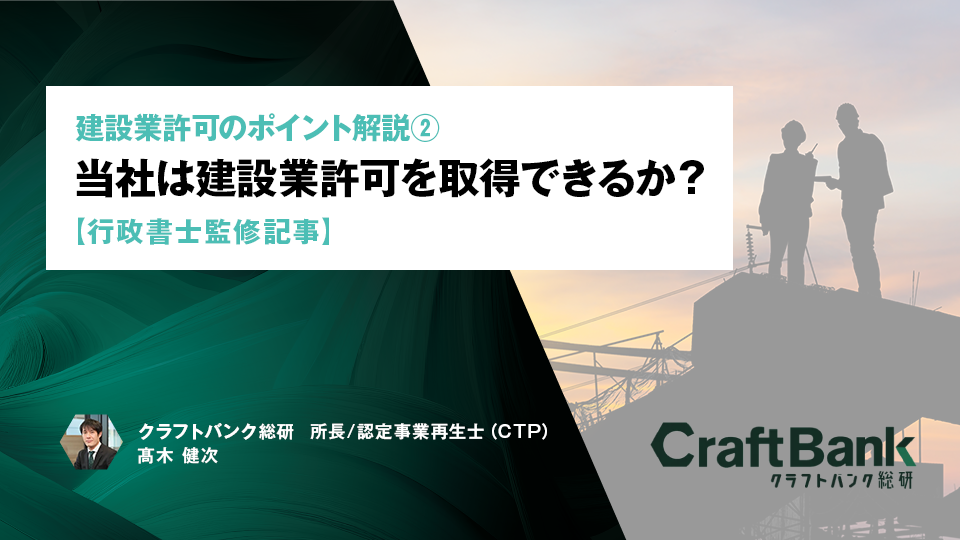建設業許可申請のポイント解説② 当社は建設業許可を取得できるか?【行政書士監修記事】
更新日:2025/4/17
-
当社は建設業許可を取得できるか?
-
29工種の中からどの許可を取得すべきか?
-
許可の取り消しについて
建設業に関わる方でこういった疑問をお持ちの方向けに、2回に分けて建設業許可申請について記事を配信しています。
特に独立や建設業許可を新規取得して工事業に参入を検討される方にとっては重要な内容になっています。
なお、本記事は前回(そもそも誰に相談する?)に続き、行政書士法人みそら(静岡県)の代表・塩崎宏晃先生に内容を監修いただいています。
https://www.misora.or.jp/kensetsugyo/kensetsukyoka/
非常に複雑な内容ですので、塩崎先生を始めとする「建設業に強い行政書士の先生」に相談されることをおすすめします。前回記事の通り、行政書士の先生でも建設業許可を取り扱っていないこともありますので、ホームページ等で建設業における実績を確認されることをおすすめします。
▼目次
当社は建設業許可を取得できるか?
「自分は資格を持っているから建設業許可も取れる」とは限りません。
「サラリーマンを辞めてすぐに起業」した方が建設業許可を取得するのは、かなりハードルが高いです。
建設業許可を取得するためには6つの条件があります。(建設業法第7条、8条、令和2年改正建設業法)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/16bt_000082.html
①建設業の経営経験5年以上ある管理責任者である
②「二級電気工事施工管理技士」等の有資格者や実務経験者などの専任技術者が在籍
③過去に建築士法、宅地建物取引業法等に違反していない
④500万円以上の自己資本または資金調達能力
⑤社会保険に加入
⑥禁固以上の刑や労働基準法違反等で罰金刑等に処せられていない
以下、詳しく見ていきます。
① 経営業務の管理責任者がいること
- 許可を受けようとする業種について5年以上経営業務の管理責任者(常勤の取締役など)として経験を有する
- 上記と同等以上の能力を有すると認められた者
例:建設業以外の業種の経営経験が5年以上あり、建設業で2年以上役員等としての経験を有する者とその役員を直接に補佐する者を配置している
上記を確認するために登記簿謄本等を提出する必要があります。「部長」「執行役員」の経験が「経営業務の管理責任者」に該当するかは個別に専門家に確認が必要です。
https://www.mlit.go.jp/common/001365752.pdf
② 営業所ごとに専任技術者がいること
- 各営業所単位で、その営業所専任(兼務は×)の技術者が在籍していること
専任技術者に求められる資格は一般建設業許可(一般と特定の違いは前回の記事参照)の場合、以下のいずれかを満たす必要があります。
- 二級電気工事施工管理技士、二級土木施工管理技士などの国家資格
- 10年以上の実務経験
- 指定学科を卒業して実務経験が3~5年ある(電気工学科、土木工学科など)
国家資格は資格証を提出すればよいですが、実務経験は雇用保険被保険者証の写し(現職だけでなく前職分も)、指定学科の卒業は学校の卒業証明も必要です。
建設業許可取得の際に、書類を集めるのが最も困難と言われるのがこの専任技術者の証明です。
実務経験は施工経験である必要があり、現場の雑務や事務作業経験は対象になりません。
また、①の経営業務の管理責任者が②の専任技術者を兼務することは可能です。
③ 請負契約に関して不正や不誠実な行為をする恐れが無いこと
建築士法などの法律に違反し、免許取消処分を受けて5年を経過しない者が申請者である場合などは取得できません。
④ 請負契約を履行するに足りる財産的基礎があること
一般建設業許可の場合、以下のいずれかに該当すること。
- 自己資本の額が500万円以上
- 500万円以上の資金を調達する能力(担保不動産がある、銀行の融資証明があるなど)を有する
- 許可申請直前の過去5年間許可を受け、継続して営業した実績を有する
⑤ 適正な社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)への加入
令和2年の改正建設業法において新たに義務化されました。
⑥ 欠格要件に該当しないこと
欠格要件には次のようなケースが当てはまります。
- 許可申請書等に偽りの記載がある
- 役員や営業所の代表者等が次の要件に該当する
- 破産者で復権を得ない者
- 建設工事を適切に行わなかったために公衆に危害を及ぼした時
- 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行の終わりの日から5年を経過しない者
- 建設業法、労働基準法、都市計画法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律などに違反したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行の終わりの日から5年を経過しない者
29工種の中から、どの許可を取得すべきか?
https://www.mlit.go.jp/common/001209751.pdf
先述の管理責任者、専任技術者の要件を満たすのが困難ですので、まず「社内にどんな資格や経験を持つ人材がいるか」から考えるのが良いでしょう。
| 略号 | 建設工事 | 例示 |
| 土 | 土木一式工事 | 橋梁工事やダム工事、空港工事などを一式として請負う工事 |
| 建 | 建築一式工事 | 建築確認を必要とする新築及び増改築 |
| 大 | 大工工事 | 大工工事、型枠工事、造形工事 |
| 左 | 左官工事 | 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事 |
| と | とび・土木・コンクリート工事 | とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据え付け工事、工作物解体工事 くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事 コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外溝工事、はつり工事 |
| 石 | 石工事 | 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事 |
| 屋 | 屋根工事 | 屋根ふき工事 |
| 電 | 電気工事 | 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事、避雷針工事 |
| 管 | 管工事 | 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水、給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事 |
| タ | タイル・れんが・ブロック工事 | コンクリートブロック積み(張り)工事、れんが積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿スレート張り工事 |
| 鋼 | 鋼構造物工事 | 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事 |
| 筋 | 鉄筋工事 | 鉄筋加工組立て工事、ガス圧設工事 |
| ほ | 舗装工事 | アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事 |
| しゅ | しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事 |
| 板 | 板金工事 | 板金加工取付け工事、建築板金工事 |
| ガ | ガラス工事 | ガラス加工取付け工事 |
| 塗 | 塗装工事 | 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事 |
| 防 | 防水工事 | モルタル防水工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事 |
| 内 | 内装仕上工事 | インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事 |
| 機 | 機械器具設置工事 | プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事(ガスタービン等)、集塵機器設置工事(トンネル、地下道等の)、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事 |
| 絶 | 熱絶縁工事 | 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備または燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事 |
| 通 | 電気通信工事 | 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事 |
| 園 | 造園工事 | 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事 |
| 井 | さく井工事 | さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事 |
| 具 | 建具工事 | 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事 |
| 水 | 水道施設工事 | 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事 |
| 消 | 消防施設工事 | 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発製液体または粉末による消火設備工事、野外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋または排煙設備の設置工事 |
| 清 | 清掃施設工事 | ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事 |
| 解 | 解体工事 | 工作物解体工事 |
許可の取り消しについて
参考
https://fstg.co.jp/blog/procedure/839
https://vs-group.jp/gyoseiss/gyosho/penalties
建設業許可を受けるための要件を維持できなくなったために許可を取り消される場合があり、「手続き上の取消し」と言われます。
以下の二点に該当すると許可は取り消しになりますが、取り消し理由を解消すれば再度許可申請が可能です。
「管理責任者」と「専任技術者」の欠員
①管理責任者、②専任技術者を後継者不足、人手不足の中で維持・確保するハードルが高いです。
許可に必要な経営者の病気、体調不良や資格者などの専任技術者の転職・退職は許可の取り消しにつながります。
企業買収(M&A)の際もこの建設業許可に関わる人材の転職・退職が無いように進める必要がありますし、逆に買収によって有資格者等を確保できれば、新規の許可取得も可能になります。
欠格要件に該当
例えば、会社の代表者・役員が飲酒運転で深刻な人身事故を起こし、自動車運転処罰法等に基づいて禁固以上の刑に処された場合等も許可の取り消しになる場合があります。
2024年4月以降の時間外労働の上限規制に反して会社の代表者が罰金刑を受ける(労働基準法違反)になると、建設業許可の欠格要件や監督処分の違反行為に該当し、最悪の場合、営業停止や建設業許可の取り消しに繋がる恐れがあります。
「今度会社を買収するけど、経営者が高齢で引退する予定。こういう場合、建設業許可の維持はできる?」などは専門性の高い行政書士の先生に相談することをおすすめします。
監修:行政書士法人みそら(静岡県)代表・塩崎宏晃先生
https://www.misora.or.jp/kensetsugyo/kensetsukyoka

日本行政書士会連合会 03171958
静岡県産業振興財団 登録専門家
建設キャリアアップシステム認定アドバイザー
この記事を書いた人

クラフトバンク総研 所長 / 認定事業再生士(CTP) 髙木 健次
京都大学卒。事業再生ファンドのファンドマネージャーとして計12年、建設・製造業、東日本大震災の被害を受けた企業などの再生に従事。2019年、建設業界の経営に役立つデータ、事例などをわかりやすく発信する民間研究所兼オウンドメディア「クラフトバンク総研」を立ち上げ、所長に就任。テレビの報道番組の監修・解説、メディアへの寄稿、ゼネコン安全大会、業界団体等での講演などに従事。著書「建設ビジネス」。国土交通省「第4回今後の建設業政策のあり方に関する勉強会」臨時委員。
・YouTube出演
「石男くんの建設チャンネル(@construction-Youtuber)」にて多数出演