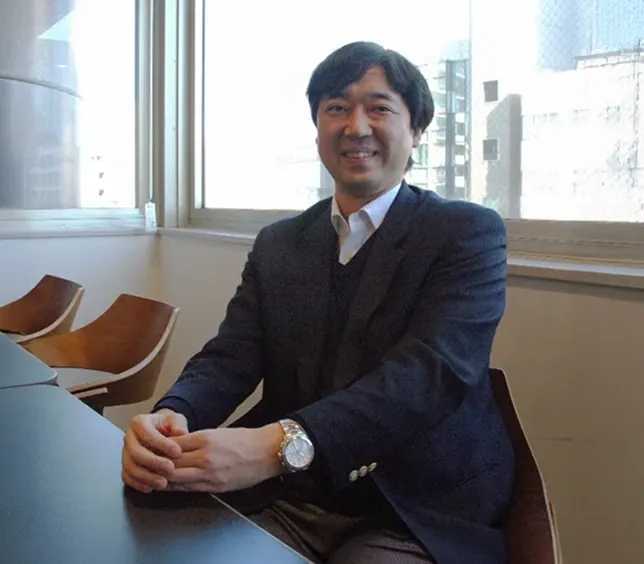ショールーム開設のハマニ。左官技術の伝承に全力を尽くす
更新日:2025/5/26
「とにかく職人の採用・育成の改革が急務だと感じた」。

左官・土木工事を手掛けるハマニ(静岡県浜松市)の河合滋社長は、慣習として続けてきた「見て学ぶ」「技術を盗んで覚える」という従来の職人文化に限界を感じ、体制の移行を決断した。新たな育成体制では、過去の仕組みを抜本から見直すことで、定着率の低さや世代間にあったギャップの克服を志向。職長会議で毎月の方針を共有する他、ベテラン職人が入社後1ヶ月を手厚くサポートするなど、組織全体で育成の方向性を統一する構成に変えた。結果は功を奏し、「定着率は10%から50%以上に向上し、職人の平均年齢も35歳まで若返らせることができた」と胸を張る。


この取り組みに関して、河合社長は「まず左官業に関心を寄せ、入職への導線を構築するには畔塗りの体験が必要と感じた。実際に手を動かすことで仕事の魅力を感じてもらい、技術習得への意欲を高める狙いがあった」と経緯を語る。現在は、中途採用も積極的に進めており、経験の有無に関わらず挑戦できる環境の整備も加速化させている。左官と大工は長年、建築業界の中核を担う職種として尊重されてきたが、工法の進化などにより変革を迎えようとしている。この過渡期をどのように維持し、発展させられるかが問われる中、河合社長は「左官の技術は、今なお世界中で求められ続けている。決して廃れることのない仕事だと確信しており、この普遍的な価値こそ伝承しなければならない」と見立てを話す。それ故に、現段階から若い世代に向けた、仕事自体に対する魅力発信・技術の継承が重要と捉えており、「この継続こそが業界の未来を左右する鍵となる」と確信しているようだ。


左官の技術は、経験を通じて蓄積した職人の知恵が大きな要素を占めるもの。「確かに体系化された学習資料は少ない。しかし、だからこそ実践を重ねながら技術を磨く環境づくりがより一層求められている」と分析する。2023年4月には、若手の主導によりショールームを開設した。実践を通じた学びの場を提供により、若手職人が更なる躍進を見せることに期待を寄せる。河合社長の原動力は「未来を担う若い社員が活躍できる職場環境を用意し、建設業界全体を活性化すること」。単純に仕事を続けるだけでなく、メリハリを持って働けることで、より成長を実感できるはずという意向は誰よりも強い。業界内には課題も山積する状況だが、「経営者側の工夫次第で、左官という伝統を引き継げる」という揺るぎない自信もある。筆者は、河合社長が掲げる「時代の変化を受け入れながらも、常に改善・改良を繰り返し、建設業界の発展に繋げたい」という基本スタンスこそ、専門工事会社の模範かつ鏡として浸透すべきだと考えている。


この記事を書いた人

クラフトバンク総研 記者 川村 智子
新卒で入社した建設コンサルタントで、農地における経済効果の算定やBCP策定などに従事。
建設業の動向や他社の取り組みなどに興味を持ち、建通新聞社では都庁と23区を担当する。
在籍時は、各行政の特徴や課題に関する情報発信に携わる。2024年よりクラフトバンクに参画。
記者として企画立案や取材執筆などを手掛けている。