「持続可能」な循環を後世に。長瀬土建が森林空間の有効活用に挑戦
更新日:2025/5/2
「建設業は災害対応で地域を守るが、森林整備も同時に行うべきと考えた」。
岐阜県を中心に公共土木工事などを行う長瀬土建(岐阜県高山市)が、林業の事業化を開始したのが2010年。長瀬雅彦社長は、たかやま林業・建設業協同組合の立ち上げ時から専務理事を務め、地場に根付いた建設企業と協働で、飛騨高山地域の森林経営計画や、各研修会などを定期的に開催。東京都と同じ面積に当たる広大な高山市を組合員19社で担当分けし、高性能な林業機械の活用や、地域に合った低コスト木材生産システムの確立などを手掛けている。


長瀬土建は、創業初期から土木工事業・砂利・採石工事業を行ってきたが、長瀬社長が代表取締役に就任して間もなくして、環境配慮および開発行為の規制などの観点から撤退を決断。これは、4年前から取り組みを開始したSDGs活動の原体験にもなっており、「当社が、温室効果ガスの排出削減量・吸収量をクレジットとして国が認証する『J-クレジット制度』と『脱炭素』、『SDGs』の3部門を繋げ、建設業界に促進する大きなきっかけになった」と振り返る。林業の分野では、日本の50年以上も進んでいると言われるドイツを合計30回以上も訪問し、現地で活用する仕組みを習得。この経験から「森林で1番優先すべきは、国土の保全・保安」という前提に立ち、高山市で天変地異が発生した際は、道路の排水が分散するシステム構築を実現した。

長瀬社長は、「災害時に建設企業が発動するのは至上命題だが、最も重要なのは災害自体を把握し、後世の人々に伝承していくこと。『復旧したら終わり』と単発では終わらせず、ストーリーとして原因・経緯・結果を記録する必要性を地域・行政・各企業・社員・将来を担う子供達に繋げることが大切」とポイントを話す。実際に飛騨高山で2020年に豪雨が巻き起こった時には、長瀬社長が自ら現場で写真撮影し、会社ホームページやSNSなどにアップを繰り返した。この「記録→検証→対策→広報」という循環を組織内に定着した実績を受け、現在の高山建設業協会のホームページにある、年間SDGsの取り組みの全てを長瀬社長が作成するようになったという。

これまで地元の保育園や幼稚園、小中高生との交流も積極的に行ってきた通り、長瀬社長は「将来を担う子供たちは文字通り宝」と断言。昨年、高校・大学生を対象に開催したインターンシップでは、23人の生徒が参加し、長瀬社長の建設ICT・林業やドイツでの体験に関する講演を実施。これまでと違う視点で仕事に着目することで、「首都圏で就職して経験を積んだ後、その知見を持ち帰り地元の活性化に繋げたい」と話す生徒も年々増えている。週休2日を含めた働き方改革も早期に導入したこと、また林業の経験から「持続可能」をテーマに、環境保護とビジネスの両輪を同時に進める点などが若者には斬新で、長瀬社長の講演は全国各地でも「他者を惹きつける」と評判になっている。

「現在は、森林空間の利用という観点で、今年廃止を予定している高山市のスキー場に、キャンプや食、森林浴、環境教育、ワイナリー、カヤックなどを行える場を整備する構想を、高山市や各企業と進めている。個人的には、この壮大な構想を実現できるのはマッチングができる建設業しかないと確信している。前途は多難だが、当面はこのプラットフォームを作り上げることができるよう、注力していきたい」と展望を語った。長瀬社長の目標は、高山市民に広い意味で「近所のコンビニよりも、長瀬土建を必要とされる存在に」という概念が行き渡ること。常に時代より一歩先の取り組みを見せ、堅実かつ着実に歩みを進めてきた、長瀬土建の次の一手から目が離せない。

この記事を書いた人
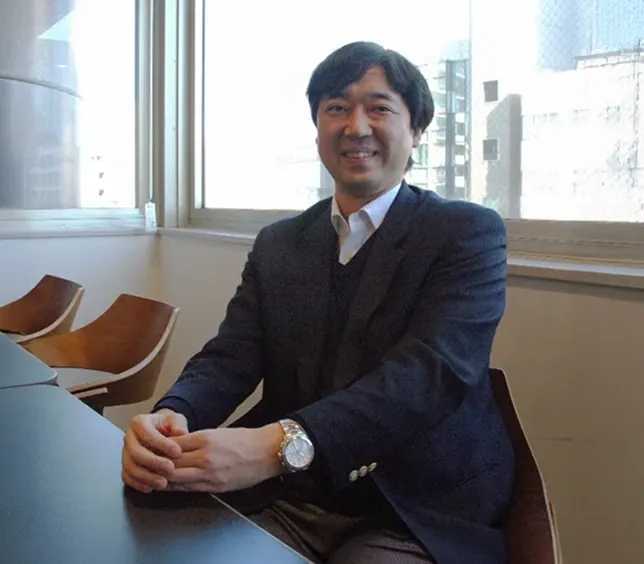
クラフトバンク総研 編集長 佐藤 和彦
大学在学時よりフリーライターとして活動し、経済誌や建設・不動産の専門新聞社などに勤務。ゼネコンや一級建築士事務所、商社、建設ベンチャー、スタートアップ、不動産テックなど、累計1700社以上の取材経験を持つ。
2022年よりクラフトバンクに参画し、クラフトバンク総研の編集長に就任。企画立案や取材執筆、編集などを担当。現在は全国の建設会社の取材記事を担当。









