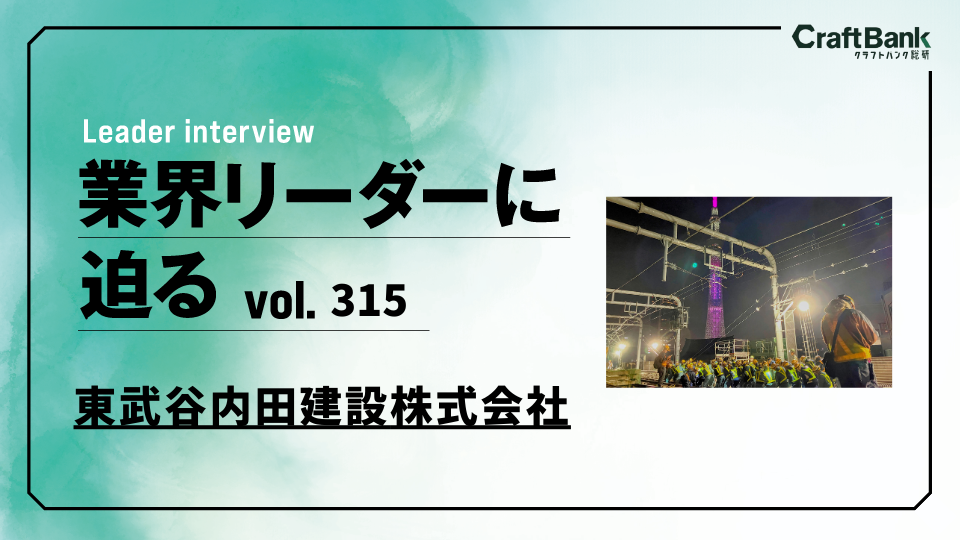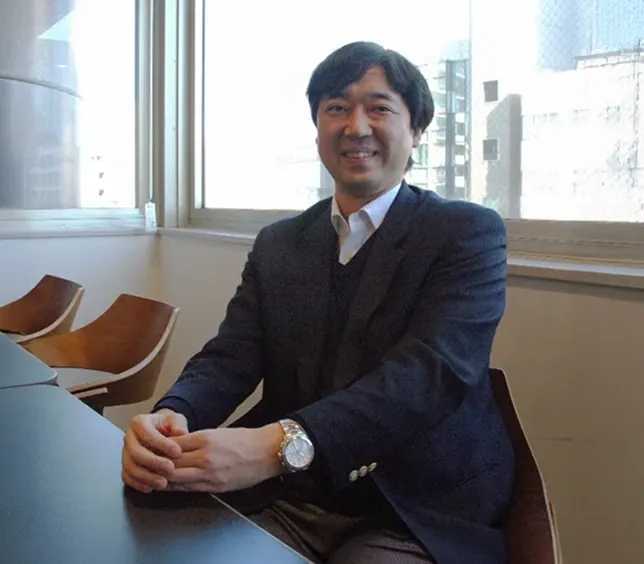大島造園土木が、「緑の価値を高める」活動に注力
更新日:2025/9/24
造園の過程における設計と施工、その後の維持管理を一手に担う大島造園土木(名古屋市中区)。大島健資社長は、「創業以来の教えである『身の丈にあった経営』で造園業を更に深化させていく」と長い歴史の中で継承されてきた基本スタンスを示す。


学生時代は家業を継ぐ意志はなく、新卒では異業種に就職した。しかし、新たな職場と自宅の中間点に大島造園土木が存在しており、出勤時に5代目社長である父から自社の経営方針や事業課題を聞いたこともあり、「経営者という重責に挑戦したいという思いが、ふつふつと湧き上がってきた」と当時の心境を振り返る。心機一転を図り転職を果たした2000年以降、公共事業は大幅に削減されていくこととなる。間もなく「改革が必須」と痛感し、採用強化の推進に舵を切った。社員を募るために作成した自社のホームページでは、自らが率先してコードを打つなど工夫を凝らした甲斐もあり、当時80人だった社員数を現在の約200人に拡大することに成功。「一連の取り組みを経て新卒で入社した社員が、今では中堅に成長し、会社の発展に貢献してくれるようになった」と語る姿が何とも誇らしそうで印象的である。


2010年の代表取締役に就任直後、大島社長は「1872年の創業時から築き上げた知見を活かしつつ、新規事業に取り組むバランスを大切にする」と決意を新たに提示した。自社の強みは、「100人以上の施工管理技士が、緑化専業を強みに各々が歴史を背負い、プロフェッショナルとして自覚を持っていること」。多様化するニーズに対し、日々研鑽した確かな造園・外構・緑地維持管理の技術など、様々な緑を高めるソリューションを用意しており、最先端で活躍する企業として、現在進行形でアップデートを繰り返している。近年では、社員が開発した独自技術が活き、様々な表彰を受けるなど業界を特有の形で牽引しており、今後どのような変貌を遂げていくか興味深い要素である。


「現在の市況には一服感がある」と分析する一方、ウェルビーイングやSDGsが注目されるなど、「緑の価値」が今まで以上に重視される時代。この流れを追い風に、大島社長は「緑地整備や生物、多様性など、総合的な需要に応じることも意識していく」と先を見据える。取材中には、何度も「歴史に甘んじることなく、社会のニーズを的確に見極め、愚直に技術を追求する」という固い決意を聞くことができた。原動力は「多くの人々の幸せにするために、技術・空間・未来を『つくり』続けていくこと」。社内では、これまでにない程の個々のスキルとチームワークが発揮されている。「これからも果敢な挑戦を続けることで、当社と関わる皆さまを笑顔にしたい」と語る大島社長の表情には一点の曇りはなく、これからどのような変遷を辿りながら、業界全体の緑の価値を高めていくのか注目である。


この記事を書いた人

クラフトバンク総研 記者 信夫 惇
建通新聞社に10年間勤務。東京支局・浜松支局・岐阜支局にて、県庁などの各自治体や、建設関連団体、地場ゼネコン、専門工事会社などを担当し、数多くのインタビューや工事に関する取材に携わる。
2024年にクラフトバンクに参画。特集の企画立案や編集、執筆などを手掛けている。