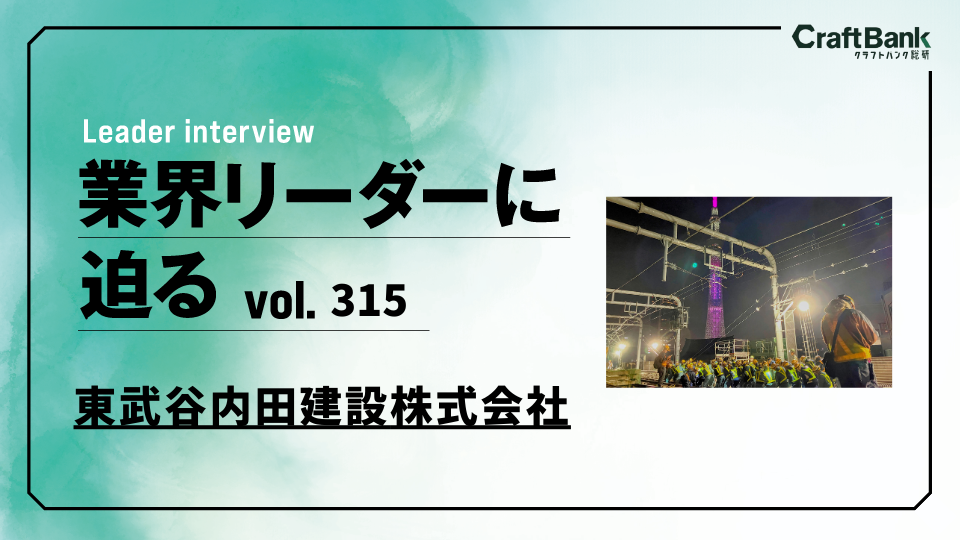ダンピング防止の仕組み化に期待。練成工業が先を見越した活動を推進へ
更新日:2025/5/2
現在、中央建設業審議会(中建審)・社会資本整備審議会合同の基本問題小委員会で、「標準労務費」に関する考え方を策定している。これは、国土交通省が受注者による廉売行為を制限する基準や、賃金の行き渡りに関する具体的な範囲や内容などを制定するもの。練成工業(東京都練馬区)の岡田宏章社長は、「当社のような専門工事会社にとって、この『標準労務費』が定着し、いかにダンピング防止に繋がる仕組みを作れるかが最大のポイント」と断言する。岡田社長は、建設産業専門団体連合会(建専連)の企画委員会(日本型枠より派遣)にも所属し、現在は標準請負単価の設定を模索。ゼネコンが専門工事業者に対し、基準より安い価格で発注した場合、中建審から勧告するシステムの確立を期待しており、「現在地が型枠を含めた専門事業者にとって正念場を迎えている」と捉えている。


岡田社長が、ダンピングの事前予防・安定した請負価格にこだわる理由は、専門工事業の収益構造が脆弱なことに加え、元請けなどから賃金を差し引かれるケースが多く、携わった工事でも結果として赤字に陥る要素が多いから。不当廉売のない環境を確約することで、職人に対する正当な給与を保証し、業界内の離職・倒産の防止に繋げることを目論む。無事に浸透した場合は、発注者に対しても賃金台帳を提示すれば、職人への支払いが証明できるなどメリットは多いと考える。現在、建専連が取り組む内容の結果次第では、専門工事業者の行く末が決定付けられる可能性が高い。

練成工業では、数年前から「同じ型枠でも何か特色を見せること」を目的に、ペリー・ジャパン(同中央区)のシステム型枠を大量購入した。まだ活用の機会は限られているが、物流倉庫など大規模な施設の施工時に、安全・品質の向上や省力化、工期短縮などの効果があるという。レンタルでなく購入した動機を聞くと、「姉歯事件やリーマンショック以降も力強く生き残っている企業の共通項は、人や設備など何かしらに意図を持って投資を実施していたことだった。『本業が不調でも必要以上にダメージを最小限にするよう、安定的な収入を得られる柱を確保する』。この点を留意し組織経営を試みてからは、資金繰りに余裕を持って取り組めるようになった」と振り返る。岡田社長自身も10数年前から、実習生の住居確保や固定経費の補助的な意味も勘案し、アパート・マンションなどの不動産経営に着手。工事費を不当に買い叩かれることもなくなり、従業員に真っ当な給与を払えるよう変化したことは、「何より離職者が極端に減り、社内が前向きな雰囲気で溢れるようになった」と話す。経営者は、常にニ手三手先を見据える必要があるが、練成工業がその領域に入る手前に除去すべき障壁が「業界の構造的なダンピング」であった現実は、根深い問題として強調しておく必要がある。

岡田社長は、自身が完全引退する時期を60歳になる6年後に設定。引退までの時間に課題として挙げている、「職人の技術承継やDXの導入を含めた生産性向上を解決しなければならない」という強い信念を持つ。次の経営は、「現在、取締役を務める3人に任せる」と宣言しており、「この決断が失敗に終われば、経営者としての私は落第点となる」と覚悟を覗かせる。常に結果を出すことに試行錯誤してきた、岡田社長を象徴するような潔い姿勢が何とも印象的である。「残り少ない経営者としての時間は、当社の世代交代・事業承継に全力を尽くす一方、子供たちが『夢は大工』と純粋に思える環境作りにも取り組みたい。業界全体を見渡しても少子高齢化は深刻で、『いかに建設業が人の役に立ち魅力的か』を発信する必要性は日に日に高まっている。当社では、この抗えない流れに少しポジティブな要素を加えられるよう、会社一体となった活動を続けていく」。

この記事を書いた人
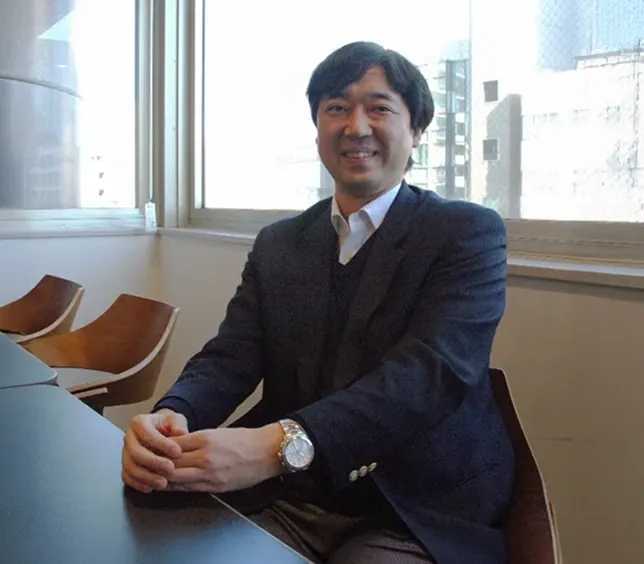
クラフトバンク総研 編集長 佐藤 和彦
大学在学時よりフリーライターとして活動し、経済誌や建設・不動産の専門新聞社などに勤務。ゼネコンや一級建築士事務所、商社、建設ベンチャー、スタートアップ、不動産テックなど、累計1700社以上の取材経験を持つ。
2022年よりクラフトバンクに参画し、クラフトバンク総研の編集長に就任。企画立案や取材執筆、編集などを担当。現在は全国の建設会社の取材記事を担当。