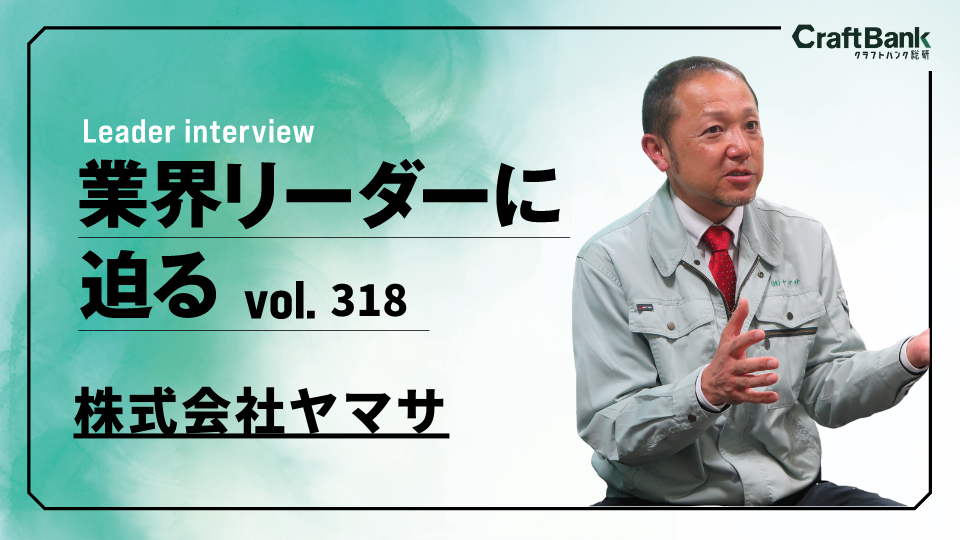創立70周年の八木建設が、「地場ゼネコン」としての定着に挑む
更新日:2025/10/30
今年3月10日に八木建設(埼玉県本庄市)が創立70周年を迎えた。現在、4代目の社長を務める人物が八木雅之氏。祖父・八木孝三郎氏を創業者に、代々受け継いできた代表のバトンを2020年に引き継ぎ、会社を牽引している。これまで時代の流れに合わせ鉄骨での施工や二重折板による高断熱工法などを導入。非住宅の木造化を推進した直後には、ウッドショックが巻き起こるなどアクシデントもあったが、SDGs達成に向けた取り組みも積極的に進めている。次の区切りとなる80周年に向けたコーポレートメッセージ(パーパス)を、「人と環境にやさしい マチ・ヒトづくり」に設定。この期間を「建物をつくる技術や知識だけでなく、人材育成にもより力を入れる10年にする」と並々ならぬ意気込みを見せている。



八木社長は、「来年4月を目処に、社内に新たな教育体制を創設するよう準備を始めている」と現況を述べる。創業から培ってきた確かな技術・経験は蓄積されている。しかし、社員の年齢層の割合を冷静に見ると、60歳以上が3割程度に増えており、「現段階から未経験からでも1年ほど学べば、施工管理者としてのスタンスが身に付くカリキュラムの策定が必須と感じた」と率直に語る。OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)だけでは、賄いきれないプロジェクト。近年、新卒として入社する社員は「『この過程をきちんと踏めば、順調に成長できる』という、学校のようなプログラムを提示できると安心する」との傾向を把握し、会社としての知見を継承する仕組みを総力で作り上げている。間もなく中途で入社する社員も、大手ゼネコンで現場監督として活躍したシニアを予定しており、若手だけでなく会社全体を強化する貴重な人材として、存在感を発揮していく方針である。



この数年間、八木建設では過去最高の売上高を更新し続けている。この状況を歓迎しつつも、八木社長は「直近の目標としては、『地場ゼネコン』と定義される売り上げ30億円を、無理なく続けられる会社を目指している」と明言する。おそらく2年続けて経営事項審査(経審)に「売り上げ30億円以上の企業」と記載されれば、入ってくる情報も変化し、新たな糸口を掴める契機にもなる。この状況を「スタートライン」として、現在は更なる飛躍を遂げられる組織作りを急ピッチで進めている。会社の経営理念は「まちづくりで社会貢献し、顧客に感動を 社員に幸福を」。取材中、八木社長は何度も「社員とその家族に喜ばれる活動を続ける」という意思を明確に示しており、常に「風通しの良い職場にするために改善を続ける」と強い意欲を見せていた。次の10年に向けた挑戦は既に始まっている。この先、八木建設が見せていく特有の発展過程から目が離せない。



この記事を書いた人
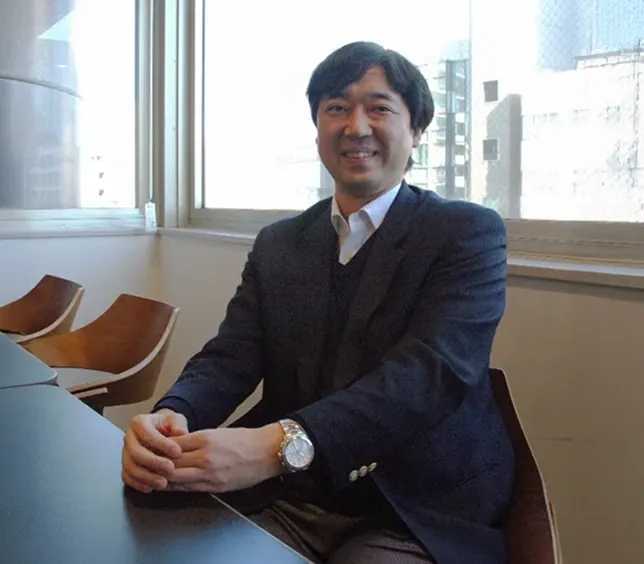
クラフトバンク総研 編集長 佐藤 和彦
大学在学時よりフリーライターとして活動し、経済誌や建設・不動産の専門新聞社などに勤務。ゼネコンや一級建築士事務所、商社、建設ベンチャー、スタートアップ、不動産テックなど、累計1700社以上の取材経験を持つ。
2022年よりクラフトバンクに参画し、クラフトバンク総研の編集長に就任。企画立案や取材執筆、編集などを担当。現在は全国の建設会社の取材記事を担当。